略歴
1975年生まれ。名古屋大学大学院文学研究科博士課程後期修了。福岡教育大学准教授、同大学教授を経て、現在本学科教授。
学習院大学
文学部日本語日本文学科
大学院 人文科学研究科日本語日本文学専攻
Staff
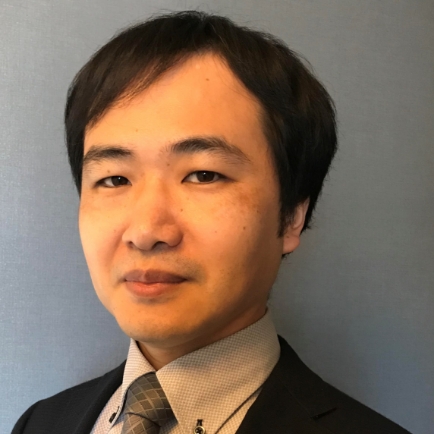
KATSUMATA, Takashi
1975年生まれ。名古屋大学大学院文学研究科博士課程後期修了。福岡教育大学准教授、同大学教授を経て、現在本学科教授。
古代日本語・日本語文法史
担当授業(2025年度)
主要論文
所属学会
日本語学会(2015.6~2018.5 大会企画運営委員)/日本語文法学会/日本言語学会/萬葉学会/訓点語学会
上代や中古を中心とした古代日本語、特に文法の歴史的研究を専門にしています。これまでに、連体形終止文、係り結び(ソ(ゾ)、コソ)、形式名詞述語文(モノソ(ゾ)、モノナリ)等について研究を行ってきました。これらは古代日本語の文終止体系とその動態について記述・考察することを念頭に置いた研究の一部です。最近は文終止に限らず、従属節についても考えるようになりました。たとえば、「係り結びの法則」は、高等学校でも教わった記憶がある人が多いと思います。今さら研究することなど無いと思われそうですが、実はわかっていないこともたくさんあります。たとえば、「ぞ」「なむ」「こそ」は「強調」を表す(が、現代語訳はしなくてよいことも多い)と一般には言われています。しかし、一口に「強調」といってもいろいろありますし、実例を丁寧に見ていくと、強調されているようには読み取れない例にもしばしば出会います。「ぞ」「なむ」「こそ」の違いについても、どうも決め手に欠けているのが現状です。現代語の「のだ」文との類似も指摘されますが、違っている点も少なくありません。古代語と現代語では具体的にどう違っているのか。なぜ違っているのか。どういう経緯で、なぜ、そのときに変化したのか。わかっていないことはまだまだたくさんあります。
私の専門領域である日本語学は、日本語母語話者が常日頃当たり前のように話している日本語そのものが研究対象です。授業では、身近すぎて「当たり前」になっている「日本語」そのものを見つめ直す視点を持つことを大事にしています。日本語を改めて知ることで言葉に対する興味や関心が育ちます。またその歴史から現在使っている日本語が、古代から連綿と受け継がれ少しずつ変化してきたものであることを知ることで、言語を客観的に観察する力が身につきます。卒業研究や学位論文においては、学生の皆さん自身の興味や関心を中心にテーマを決めてもらいます。誰かに決めてもらうのではなく、自ら学び、疑問点を見つけ、調べ、考え、新たな発見の喜びを知ることで、研究が自分のものになります。また、演習や中間発表等のプレゼンテーションや議論の場は、ともに学ぶ仲間との交流の場であり、多様な考え方や価値観のあり方を知る場でもあります。そこでの経験と自らの研究を通して、再び皆さん自身の価値観を新たに創造していきましょう。そうすることで、自らの成長を実感することができます。皆さん自身が自らの将来についてより深く考え、卒業後の進路を選び、やがて社会に出て活躍していく上で一つの自信となってくれることを願います。
大学で学ぶ上では、興味があることもないこともまずは触れてみて、自分にできることを探してみましょう。自分が得意なことと、興味のあることや好きなことが初めから一致するとは限りません。また、自分ができることに自分では気づかないことも多々あります。知らなかった世界を知ることで、是非自分の可能性を広げて欲しいと思います。