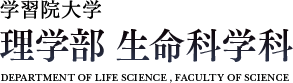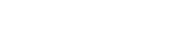生命科学科(学部)、生命科学専攻(大学院)兼務
(教授の姓の五十音順に研究室を並べています)
動物生理学
ショウジョウバエを使って、「発生・生殖・寿命のしくみ」を解明
個体発生・生殖戦略・寿命制御など、多細胞動物のもつ様々な高次生命機能は、系統樹の枝を超え、哺乳類と昆虫の間で高度に保存または収斂されている。遺伝学の研究に適したショウジョウバエなどを駆使して、これらのしくみを解明する。
【教員】
教授:安達 卓 / 助教:大塚 慧
構造生物学
X線を使って「膜タンパク質の3次元結晶構造解析」を行う
細胞の表面を形成する脂質二重膜中には、物質輸送や情報伝達など重要な機能を担う膜タンパク質も存在している。これらは水に溶けにくいために立体構造情報を得るのが困難であるが、視覚機能を担う膜タンパク質を中心としてX線を用いた高分解能解析をめざす。
【教員】
教授:岡田哲二 / 助教:永江峰幸
微生物科学
薬を作る微生物・放線菌を知り、創薬に向けたものづくりを目指す
土の中には様々な微生物が生息しています。放線菌は、土中で放射状に菌糸を伸ばしながら抗生物質を作り、他の土壌微生物達に自分のテリトリーを奪われないようにする独特の生存戦略を取っています。そのために放線菌は自分たちの生存を脅かす他者微生物を感知し応答する機構を有しています。また、放線菌が作り出す抗生物質から様々な感染症治療薬が開発されており、人類にとって重要な医薬資源微生物でもあります。私たちは放線菌を知ることで、生命の本質に迫ります
【教員】
教授:尾仲宏康 / 助教:星野翔太郎
神経生理学
複雑な脳のしくみを理解すべく新しいシナプス学の探究
脳内の神経細胞どうしをつなぐ「シナプス」は、細胞間の情報伝達を担うばかりでなく、記憶の形成過程や、アルツハイマー病・自閉症・統合失調症などのさまざまな神経系疾患(シナプス病)に深く関わる重要な部位である。私たちは遺伝子改変マウスを用い、脳内のシナプスがどのように形成され、そして、機能するのかを追究するとともに、シナプスに介入する新しい技術を開発・駆使することにより、記憶やシナプス病の分子レベルでの理解と制御をめざす。
【教員】
教授:掛川 渉 / 助教:伊藤政之
植物分子生理学
「植物の成長・分化」を遺伝子から個体まで幅広く研究
植物は光を光合成のエネルギー源としてだけではなく、外界を知るためのシグナルとしても利用している。植物が光受容体を介して受け取った光情報をどのようにその成長・分化の制御に利用しているのか、その仕組みを遺伝子や情報分子の改変を通して解明する。
【教員】
教授:清末知宏 / 助教:高崎寛則
生物遺伝資源学
ゲノム情報を用いて昆虫の環境適応と進化の機構を明らかにする
次世代シーケンシング技術の発達によって、様々な動物のゲノム情報を簡単に知ることが出来るようになってきた。高精度なゲノム情報をもとに、カイコガ科・ヤママユガ科の蛾類を材料として、食性や行動、遺伝子ネットワークの進化について研究している。
分子生物学
様々な遺伝子改変技術を用いて「ゲノム安定性維持のメカニズム」を解明する
DNA相同組換えは、遺伝的多様性獲得の原動力である一方、DNA損傷を正確に修復することでゲノム安定性維持に重要な役割を果たしている。日常的に発生するDNA損傷に対して生物は如何にしてゲノムの安定性を維持するか、その仕組みを酵母細胞等を用いて解明する。
【教員】
教授:菱田 卓 / 助教:林 匡史
分子生化学
ミトコンドリアを通して疾患・老化を理解し創薬に挑む
ミトコンドリアの機能が低下すると、老化や老化に関連した様々な病気を誘発する。私たちは、ミトコンドリア膜上におけるシグナル応答機構の解析を通して、ミトコンドリアの新たな役割を明らかにすると共に、疾患・老化機構の解明およびミトコンドリアを標的にした創薬を目指している。
【教員】
教授:柳 茂 / 助教:椎葉一心