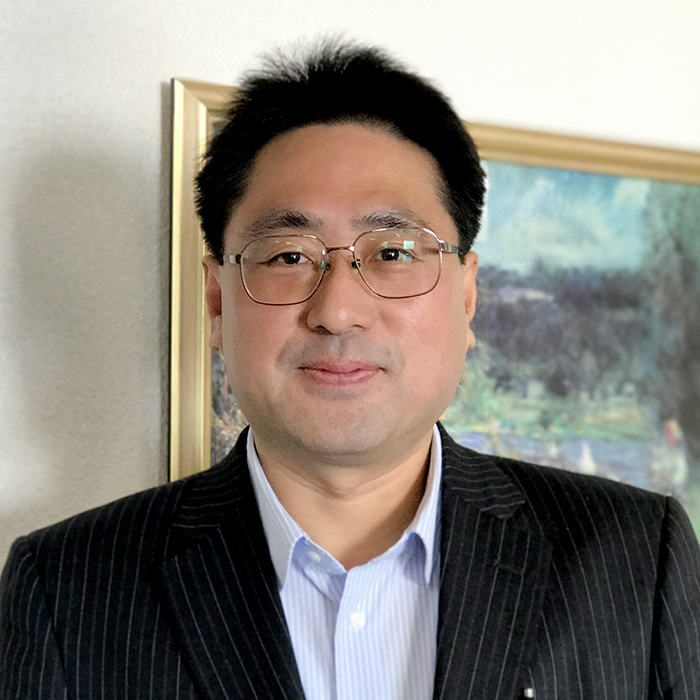
略歴
1994年 上智大学経済学部経済学科卒業
1994年〜1998年 日本銀行勤務
1999年 大阪大学大学院博士前期課程修了
2000年 同後期課程単位取得中退(2001年経済学博士取得)
2000年 大阪大学社会経済研究所助手
2001年 (社)日本経済研究センター研究員、2002年 副主任研究員
2002年 大阪大学大学院国際公共政策研究科助教授
2004年 東京学芸大学教育学部総合社会システム専攻 准教授
2008年 学習院大学経済学部経済学科准教授
2009年 同教授
主要業績
(著書)
1.『経済学者、待機児童ゼロに挑む』単著、新潮社、2017年
2.『経済学者 日本の最貧困地域に挑む-あいりん改革3年8ヶ月の全記録』単著、東洋経済新報社、2016年
3.『健康政策の経済分析: レセプトデータによる評価と提言』共著、東京大学出版会、2016年(第51回日経・経済図書文化賞)
4.『脱・貧困のまちづくり 「西成特区構想」の挑戦』編著、明石書店、2013年
5.『年金問題は解決できる-積立方式移行による抜本改革』日経新聞出版社、2012年
6.『成長産業としての医療と介護 』共編著、日本経済新聞出版社、2011年
7.『社会保障と財政危機』単著、講談社現代新書、2010年
8.『社会保障の「不都合な真実」』単著、日本経済新聞出版社、2010年
9.『年金は本当にもらえるのか?』単著、ちくま新書、2010年
10.『だまされないための年金・医療・介護入門』、単著、東洋経済新報社、2009年(第9回・日経BP・Biz Tech図書賞、第一回政策分析ネットワーク奨励賞)
11.『生活保護の経済分析』、共著、東京大学出版会、2008年(第51回日経・経済図書文化賞)
学外での活動
医療経済学会事務局長、同理事、日本経済学会代議員、雑誌「医療と社会」編集幹事
所属学会 : 日本経済学会、日本財政学会、医療経済学会
講義・演習の運営方針
経済学部に社会保障論の講義がある大学自体、非常に珍しいと思います。それだけに、教科書もほとんど無いに等しい状態ですが、次のように初学者にとって有利な特徴があります。
第一に、日々新聞やテレビなどで見聞きする現実問題との関わりが極めて密接であり、勉強する意義が分かりやすい。
第二に、経済学以外の社会学、医学、福祉学、法学等から同じ問題にアプローチされている学際分野であり、他の分野からの分析・政策提言と比較することにより、経済学の分析手法、政策提言の特徴がより鮮明となる。
第三に、分析に使われている経済学の道具立てはそれほど複雑なものではないことから、初学者でも経済学の切れ味を十分に堪能でき、経済学を現実問題に応用することの楽しさが味わえる。
社会保障論の講義に当たっては、こうした特徴を最大限に生かしたいと思っています。初めに、今まさに直面する現実の社会問題の解説を十分に行なって、これから学ぶ対象を身近に感じられるようにします。次に、厳選した経済学の基本的ツールを完全に修得してもらい、経済学的なアプローチの適用が一見難しくみえる分野に対する「経済学の応用」を練習することにします。最後に、他分野から提示されている分析、処方箋と経済学のそれを比較することにより、経済学の長所・短所を明らかにしたいと思います。出来れば、単純な講義ではなく、対話型の議論を伴うような講義をしたいと思っています。
3年生の演習については、社会保障・社会福祉の今まさに問題となっているホットなテーマについて、毎回、ディベートという形で議論したいと思います。ディベートとは、あるテーマについて賛否両論に別れ、チームごとに意見を戦わすという一種のゲームであり、少し工夫をすることにより、知らず知らずのうちに合理的な思考方法、経済学の現実問題への応用が身につきます。また、毎回、たくさんの資料・文献に当たっていただくことにより、社会保障・社会福祉についての実践的な知識を得ることができると思います。2年生の演習については、議論するテーマの対象をもう少し広げ、毎週話題となっているスポーツ、芸能、恋愛、教育、犯罪など身近な社会問題についてディベートを行なうことにしたいと思います。経済学はどのようなテーマにも応用が可能です。経済学的な思考方法を、どんな現実問題にも応用できるようになることこそが私の演習・講義の目標です。
メッセージ
私が学部で経済学を学んだのは、既に20年以上前のことになってしまいましたが、最初に授業を受けた時の感動は今でも鮮明に思い出すことが出来ます。それは、「世の中にこんなに役に立つ学問があるのか!」という衝撃でした。日々起きている複雑な社会問題を、鋭い切れ味で解き明かし、解決のための処方箋が明確に示される。そして、しばしばそれは常識とは全く逆の結論なのですが、合理的な思考・論理を辿れば、確かに経済学の処方箋は正しいと説得される、そんな経験でした。大学を卒業後、ずいぶん時間が経ち、いつの間にやら経済学が私の仕事になってしまいましたが、いまだにその感動は続いており、仕事としての苦労もありますが、やはりまだまだ経済学が面白くて仕方がありません。皆さんと経済学の出会いも、幸福なものになりますようにお祈りいたします。
最近の研究テーマ
私の研究分野は、「社会保障論」で、具体的には、年金、医療、介護、保育、少子化対策、生活保護、ホームレスといった社会問題の解決に、経済学を応用して取り組んでいます。
わが国の現役層と高齢者の比率は現在3人対1人ですが、11年後の2023年には2人対1人、2040年には1.5人対1人、最終的に2060年ごろには大体1対1となると予想されています。つまり、1人の高齢者が受け取る年金、医療、介護などの費用を、現役1人で支える社会がもう直ぐやってくるのです。これほどハイスピードの少子・高齢化を経験した国は、世界史的にもほとんどありません。これに伴って、年金財政、医療・介護財政の維持可能性が懸念され、世代間の不公平が広がっています。みなさんの中には、公的年金の保険料を支払っても支払った分だけ戻ってこず、公的年金は損だと考えている方も多いでしょう。これは年金財政を勉強すれば直ぐ分かることですが、政府が何を言おうと、事実です。
また、高齢化は所得格差拡大や貧困化の一大要因にもなっています。近年、日本社会は所得格差が拡大して、最近では貧困層の増大が問題視されており、この原因は不況が続いたことにあると思われています。しかしながら、統計的に厳密な手法によって分析をすると、景気変動要因よりも、むしろこの期間に少子・高齢化が急速に進んでいることに主因があり、したがって景気回復によって単純に解決する問題ではないことがわかります。また、少子・高齢化に伴う人口減少社会では、よほどのことが無い限り、経済成長率は低迷をすることになります。日本社会は、これら少子・高齢化に伴う諸問題にどのように対処し、乗り越えてゆくべきなのでしょうか。私の研究テーマは、一言で言うとこの「少子・高齢化への対処」ということになると思います。この日本社会が直面する大きな課題を、新しい時代を切り開いてゆかねばならない皆さんと共に勉強し、考えてゆきたいと思っています。