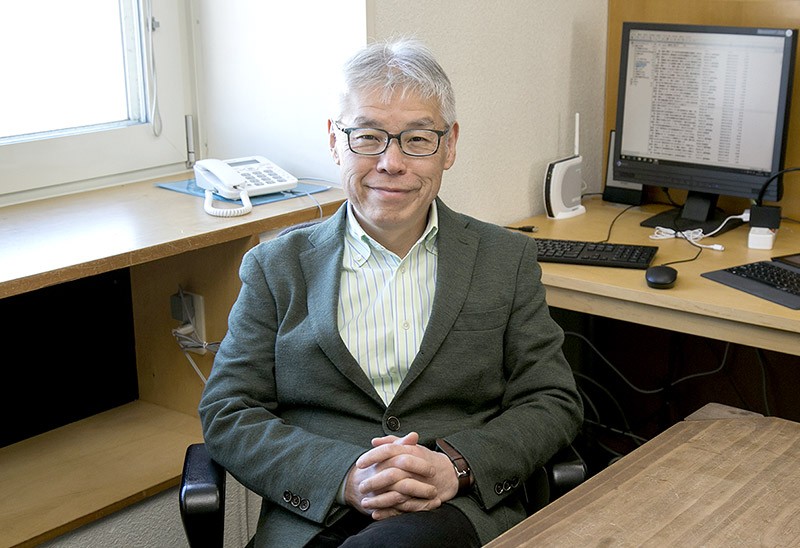
- プロフィール
- 1980年、慶應義塾大学文学部社会学専攻卒業。1986年、米国イリノイ大学産業労使関係研究所博士課程修了。人的資源管理論でPh.D.を取得。カナダ国サイモン・フレーザー大学経営学部助教授。1990年、慶應義塾大学総合政策学部助教授。1998年同大大学院経営管理研究科助教授・教授、2001年一橋大学大学院商学研究科教授を経て、2017年より現職。厚生労働省労働政策審議会委員などを兼任。著書に『人材マネジメント入門』、『人材の複雑方程式』(共に日本経済新聞出版社)、『人事と法の対話』(有斐閣)などがある。
論理と経験が融合した人事の研究者を求めて。

研究を研究で終わらせない。その先にある実現性を重視する。
守島教授は、人材マネジメント分野のオーソリティーである。そもそも人材マネジメントという言葉自体、2004年に日経文庫から出版された教授の著書『人材マネジメント入門』から一般に広まったものだ。著書は版を重ね、企業の人事部における教科書的な存在になっている。
企業の人事管理が、働く人のモチベーションや利益や業績、収益や成長性などの最終的な成果にどうつながっていくのか。守島教授は、この関係性を30年来研究している。なかでもここ5、6年取り組んでいるのが「企業における公平性という概念」だ。
「英語で言えばジャスティス、正義ということになります。正義にはいくつかの種類があって、たとえばシステムとしての正義があります。民主主義であれば一人一票を持っているとか、本人の人権を尊重するとか、それが正義になりますよね」
「企業における正義も、一つはシステムの正義です。たとえば人事で人を評価する時、システムがしっかりしていれば、AさんもBさんもCさんも同じ軸で公平に評価することができます。また、インタラクショナル・ジャスティス、対人的な正義というものもあります。これは上司が部下を尊重して扱うとか、一人ひとりの人間としての価値を考えながら部下や同僚と接するといったようなことです。企業の中にはいろんなレベルの正義があり、それが上手くまとまりながら働く人のモチベーションにつながっていくということに興味があります」
では研究を行うにあたって、どのような眼差しを持って日々取り組まれているのだろうか?
「研究の目的や目標は、人それぞれに、論文を書くためとか本を出すため、いい研究成果を世に出すためなど様々あると思います。私は私の研究対象の人たちが、より良き状態になることが重要だと考えます。私自身研究者としてのポリシーとしては研究それ自体が目的や目標ではなく、研究の<実現性>や<実践性>、<実用性>を何よりも重要視します。研究者の中では、理論を勉強し、データを採り、仮説を作り、分析をして終わりにしてしまう人が意外と多いのですね。それは決して間違いではないかもしれません。でも私としては、結果としてその先にいる研究対象者<働く人や企業>にとって、より良き状態<いかに役立ったのか>ということがポイントになります」

今後10年、研究テーマとなりうる主題とは?
守島教授は「大学院で、すべきことが3つある」という。「最初は、その分野の過去の研究を知ることです。分野といっても人材マネジメントや労使関係といった括りだと広過ぎますので、その中でたとえば公平性やモチベーション、制度でいえば成果主義、評価制度といったテーマに絞り、どういう研究がなされてきて、どういう理論があるのか、まずそれを最初に学びます」
「次に、方法論ですね。具体的な対象が出てくるわけですから、それをどのような方法で分析をしていくのか、それを学びます。統計的な方法も、質的な方法も使えるようにしておくことが大切です」
「最後は、それに基づいて自分の研究を進めることです。でも大きなことを考えてはいけません。今日まで積み重ねられてきた研究の体系に、ほんの小さな一歩が付け加えられるかどうか。知識を教え、方法を教え、それからどういう形で次の一歩を自分自身で踏み出していくのか、ということを私も一緒になって考えていきます」
時代の空気感を肌で感じているせいだろうか。院生が選ぶ研究テーマは「世の中のトレンドとシンクロしていることが多い」という。今は「女性活躍推進」や「ワークライフバランス」、「企業内公平性」などが多く、10年位前は「非正規の問題」、さらに20年位前は「成果主義」をテーマとした研究が多かったそうだ。
「もっとベーシックなことも研究してほしいのですが」と教授は苦笑する。では今後10年、どんなことが研究テーマになると教授は見据えているのだろうか。
「雇用されない働き方、と申しますか、業務委託系の働き方をする人がこれからどんどん増えますし、企業的にもそういうニーズが出てくるはずです。働く側は自分のスペシャリティで生きていくためには非常に狭い世界で能力を磨き、発揮せざるを得ない。企業側としても健康保険料や労災保険料を減らしたいので、必要な時だけ必要とする人材を調達するようになっていく。そうした中で、私は<雇用という働き方のモデル>がどんどんなくなっていくと思っています」
「その時、モチベーションや評価というものをどうするかなどが、重要なポイントになります。たとえば評価でいうと、従来は、頑張ってはいるが成果の出ない従業員に対し、長期的な評価をみたり、将来の伸びしろに賭けるということもできましたが、業務委託となると成果が出なければ評価はゼロです。そうなると今までの日本の評価体系を変えなければならない」
「また育成に関しても、今は企業がお金を出して大学を出たばかりの人たちを真っ白な形で雇って教育しているわけですが、業務委託となると必要なくなります。さらに仕事を任された時点で命じた業務は即座に遂行できるようになっていなければなりません。育成という機能が企業の中でなくなるとまでは申しませんが、大きく変わってくると予想されます。そのように働き方や労働の調達が極めてテンポラリー、短期的になると、当然人事の世界は大きく変わってきますし、そういった研究がメインストリームになると思います」

優れた研究者になるための必須条件とは?
守島教授は、人事系のイベントやセミナーでファシリテーターやパネリストとして招かれたり、政府の働き方改革の同一労働同一賃金部会で座長を務めたりと、幅広く活躍されている。そうして知り合った大手企業や新鋭IT企業の人事部の方々を大学院のゼミに招き、話を聞かせてもらう機会を設けることにも積極的だ。院生にとっては貴重な体験である。それは「土地勘を身につけさせるためだ」という。
「私は、人事の研究は企業という現場の<土地勘>みたいなものがないとできないと思っています。たとえばリーダーシップ論の話をする時、『世の中には嫌な上司っているじゃないか』と投げかけると、現場の土地勘がある人なら『ああ、あの人が私にとってマイナスの上司だったな』『企業の中で働いていると何人かそういう人がいたな』と、それが現実の世界でどのような現象なのか、良いリーダーシップ/悪いリーダーシップとはどういうものか、自分の体験と一つに結び付けて考え始めることができます。一方、そういう像が浮かばないと、良いリーダーと悪いリーダーを分ける基準が学説だけとなり、偏った分析になってしまいがちです」
守島教授は、大学院の研究室には「2種類の方々が来る可能性」があり、「おのおのに伝えたいメッセージがある」という。
「一つは、実務経験がある程度以上あり、さらに大学院で学びたいというケースです。そういう方々に申し上げたいのは、実務というのは妥協の産物ですが、理論というのは論理の世界です。両方が必要なのですが、実務から来られる方は実務で得た常識や前提を一旦棚に預けてください、というのがお願いです。一度そこから抜け出さないと良い学者にはなれません」
「補足しますと、先にも述べたように実務世界の経験は後々大変重要になります。一生懸命理論の勉強をした後、実務経験という宝物を預けた棚から出してきて、もう一度理論の目で見直していただきたい。事実は表面に現れたものなので、それが絶対真ではなくて、一定の現象として現れてきた背後のメカニズムを明らかにしてほしいと思います。ですから、それを研究するためには理論や方法論、論理的な議論といったストレートなアカデミックの世界を学ぶ必要があるのです」
事実、守島教授の院生は実務経験者が多い。たとえば指導学生の一人で、現在一橋大学の教授である島貫智行氏は、総合商社の人事部で6年勤務した後、守島教授の門を叩いた。なお実務とは人事に限らないそうだ。「大切なのは企業の現場を知っているかどうか」だという。
「そしてもう一つのケースは」と続ける。「学部から直接来る子たちは、とにかく企業の中における人の動きであるとか、アルバイト先の経験でも構いませんので実務の方々が棚に入れているもののミニバージョン、現場の土地勘というものをできるだけ早く身につけてください。それがないと、実際の人事からみたらとてもおかしなことを考えたりするのです。いずれにしても、論理と経験が融合しないと、いい人事の研究者にはなれません」
| 取材: | 2018年1月25日 |
| インタビュアー・文: | 遠藤和也事務所 |
| 撮影: | 松村健人 |
身分・所属についてはインタビュー日における情報を
記事に反映しています。
取材:2018年1月25日/インタビュアー・文:遠藤和也事務所/撮影:松村健人
身分・所属についてはインタビュー日における情報を記事に反映しています。
 インタビュー
インタビュー