
- プロフィール
- 1995年、明治大学経営学部卒業。1997年、横浜国立大学大学院経営学研究科修了。2000年、立正大学経営学部専任講師。2003年、慶應義塾大学大学院経営管理研究科修了、博士(経営学)取得。2006年、南山大学大学院ビジネス研究科准教授。2012年、中央大学大学院戦略経営研究科(ビジネススクール)教授。2013年-2014年、2017年-2018年、Johns Hopkins University, Carey Business School, visiting scholar。2024年より現職。
消費者の心理とマーケティングの接点に着目

マーケティングの視点から消費者の心理を明らかに
学習院大学大学院経営学研究科の松下光司教授は、消費者行動論を専門とする、マーケティング研究者である。消費者行動論とは、消費者が製品やサービスを購入、消費、廃棄する行動、また、それらの行動に伴われる意思決定のプロセスを対象とする研究分野である。その研究は、社会学、心理学、経済学などのさまざまな学問分野からアプローチされている。松下教授は自分自身の基本的な研究スタンスを「心理学のアプローチを採用しながら、マーケティングの視点で研究を進めています」と説明する。
松下教授によれば、マーケティングは「売れる仕組みづくり」という言葉によって端的に表現されるという。企業が自社の製品やサービスを売るための仕組みを作るうえで、多岐にわたるマーケティング活動があるが、松下教授は自身の研究スタイルを示すために、ブランドの育成を例にあげる。
「例えば、ある歯磨き粉のブランドがあるとしましょう。このブランドは緑色のパッケージで、歯周病予防を訴求点としています。消費者が、この歯磨き粉ブランドの名前、パッケージの色、訴求ポイントなどの特徴を認識していない状態では、この製品はブランドとして成立しているとは言えません。つまり『ブランド化』しているとは言えないわけです。ブランドの価値が生まれるためには、このブランドが何らかの特徴を持っていると『識別』されている必要があるわけです」
「そのブランドのマーケティング担当者としては、消費者が歯周病予防をしたければ、その歯磨き粉ブランドを買うようになってほしい。そして、そのブランドがその消費者の生活にとって、なくてはならない、というところまで持っていきたいですよね。そうなると、消費者が、歯磨き粉を選ぶときに、真っ先にそのブランドの名前や色を思い浮かべるようになるかもしれません。このような状態になると、そのブランドは『強いブランド』である、と言っても良いかもしれません」
「マーケティング担当者にとって、強いブランドを作り上げることは一つの目標です。では、そのような強いブランドを作り出すために、企業は消費者の心理にどのように働きかけることが有効なのでしょうか。そして、それはなぜなのでしょうか。このような問いが、マーケティングの視点から、消費者の心理を明らかにする研究スタイルの例です。私が関心を持っているのは、このような消費者の心理とマーケティングとの接点です」
また松下教授は、マーケティングを超えた領域にも研究の関心を広げている。消費者の行動を変える要因のひとつに他者の存在があると指摘する。このような社会的要因によって変容する消費者行動は、松下教授が取り組んでいる研究テーマのひとつだ。
「私たちの購買や消費は、一人だけでするものではありません。例えばレストランの食事を考えてみてください。食事の目的は、栄養を摂取することだけではありません。食事をともにすることで相手と仲良くなるといった、他者とより良い関係性を作るために食事をすることもあるはずです。消費者を社会的な存在として眺めたときに、食事の場面に限っても、いくつもの興味深いテーマが出てきます。もちろん、得られる結果の一部は、レストランなどのサービス企業のマーケティングにとっても、有用な知見となるはずです」
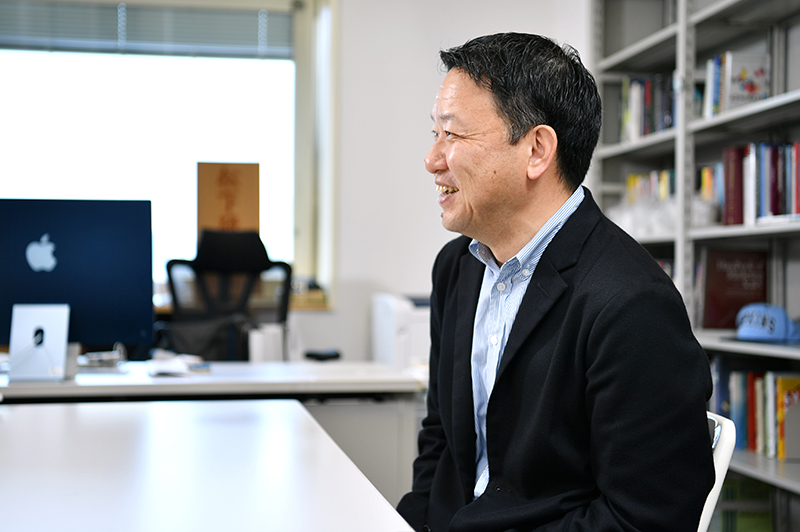
2つのターニングポイントによって導かれた研究スタイル
近年、消費者行動分析に注目する企業は増加傾向にあり、一部では専門の部署を抱える企業も登場している。しかし、日本における消費者行動研究の歴史は、さほど長いわけではない。松下教授が学部生であった1992年に学会が設立され(日本消費者行動研究学会)、本格的に日本における消費者行動研究がスタートした。
松下教授は、大学院への進学を決めた当時を次のように振り返る。
「消費者行動研究に関心を持ち、大学院への進学を考えていましたが、専門で研究されている先生は、ほとんどいませんでした。そのため、進学先として、消費者行動研究を専門とする、横浜国立大学の阿部周造先生の研究室の門を叩くことに迷いはありませんでした」
阿部教授のもとで消費者行動研究をスタートさせた松下教授は、その後、慶應義塾大学大学院経営管理研究科の後期博士課程へと進学した。同研究科は、修士課程がいわゆる「ビジネススクール」であるため、多くのビジネスパーソンとの交流を体験することになる。また、慶應義塾大学の池尾恭一先生から指導を受けたことで、松下教授は、大事な視点に気がつくことになる。松下教授は、この時期の体験を「ターニングポイントだった」と語った。
「横浜国大と慶應で学んだのはどちらも消費者行動論ですが、視点が少しずつ変わっていったんです。慶應に入る前までは消費者の心理プロセスの解明を強く意識していたのですが、慶應での研究活動で、マーケティングの影響を受けて変化する消費者の心理プロセスを明らかにする重要性が理解できるようになったのです。大学院時代にいまの研究スタイルの基本ができたわけです」
マーケティングの立場から消費者の心理プロセスを明らかにすることを、自分自身の研究の立場とした松下教授は、大学で教鞭を執りながら研究を続ける。2010年代には米国ジョンズ・ホプキンス大学で2度の在外研究の機会を得る。そこでは、各国から集まる優秀な研究者たちから大いに刺激を受けたという。この在外研究の機会が、松下教授の2度目のターニングポイントとなった。
「最前線で研究をしている人たちと交流することで、自分は日本から何を発信できるのか、発信するべきことは何なのかと、改めて考えるようになりました。研究の仕方や環境の見直しも含めて、もう一度、しっかりやらないといけないと思い直しました」
このような背景から、松下教授は自分自身ではやったことがない研究への取り組みを始める。多様なバックグラウンドを持つ人たちと力を合わせながら、研究成果を出すことにも力を注ぐようになったのである。具体的には、他分野の研究者や企業とのコラボレーションである。
「認知心理学を専門とする中央大学文学部の有賀敦紀教授らと共同し、長谷川香料株式会社の支援を得ながら、研究に取り組みました(注)。このプロジェクトでは、飲料を飲むグラスの厚みが味覚評価に影響を与えることが明らかになりました。これからも同様のプロジェクトを進めていきたいです」
(注)Ichimura, F., Motoki, K., Matsushita, K., & Ariga, A. (2023). The tactile thickness of the lip and weight of a glass can modulate sensory perception of tea beverage. Food and Humanity, 1, 180–187.

院生に必要なのは「考える姿勢」と「コミュニケーション力」
2024年4月、松下教授は学習院大学経済学部に着任した。着任して数ヶ月であるが、松下教授は、学習院の学生の姿勢や熱意を感じることができた。
「学部のゼミナール募集では、アカデミックなプロジェクトの実施に興味関心を持ってくれる学生とたくさん出会うことができました。学部のゼミナールにおいても、興味深いプロジェクトができそうだと期待を持っています。同じように大学院でも、マーケティングと消費者行動の関わりに興味を持つみなさんが集まってくれたら、面白い研究に取り組めるんじゃないかと思います」
これから学習院大学大学院での指導にも力を入れていくという松下教授。より実りある研究を修めるための姿勢を説いた。
「研究は、一方的に教えてもらうだけでは成り立ちません。自分自身で考え続けてもらうことが極めて大切です。考えることをやめない能動的な姿勢が大切です。私たち教員は、学生の皆さんが考えることをサポートする立場です」
「一人でじっくり考えることは必要なんですが、もう一つ重要なのは、考えた成果を持ち寄って議論することだと思います。良い研究に取り組むは、充実したコミュニケーションができる力も必要不可欠です。研究は、自分自身が良いと言っても、私が評価しても、成果として発表できないんです。論文は、指導教員ではない誰かの目に触れ、コメントを受けて修正し、初めて学術雑誌に発表できます。そのため、成果を周りの人たちに伝え、周囲の皆さんから意見をもらい、修正していく力をつけるべきでしょう。学習院大学のなかでも、建設的なディスカッションができるコミュニティを作り上げることが理想だと思います」
新しい環境に身を置きながら充実した研究に取り組む松下教授は、最後にこれからの研究生活の目標を語った。
「今取り組んでいるプロジェクトのなかには、海外の研究者との共同プロジェクトもあります。その研究成果を、ぜひとも学術雑誌で発信していきたいです。このようなコラボレーションを通じて得た知見を学生と共有することは、院生にとっても役に立つはずです。そうした経験を院生たちと一緒に体験できるのを、私自身もとても楽しみにしています」
| 取材: | 2024年5月31日 |
| インタビュアー・文: | 手塚 裕之 |
身分・所属についてはインタビュー日における情報を
記事に反映しています。
取材:2024年5月31日/インタビュアー・文:手塚 裕之
身分・所属についてはインタビュー日における情報を記事に反映しています。
 インタビュー
インタビュー