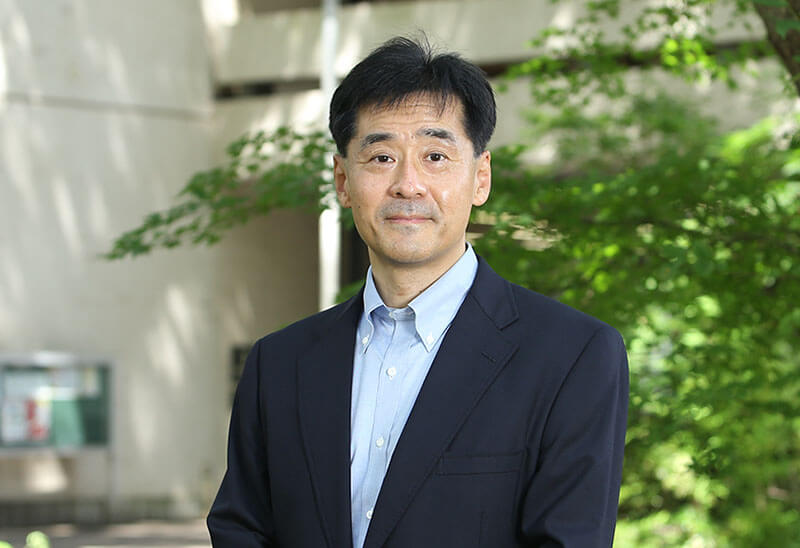
- プロフィール
- 1989年、東京大学法学部第一類卒業、1994年カリフォルニア大学バークレー校経営大学院修士(M.S.)、同大学院から2003年博士号(Ph.D.)取得。1989年郵政省入省、1992年人事院長期在外研究員に。1994年郵政研究所研究官、主任研究官を経て2000年学習院大学経済学部助教授に。2004年より現職。
特許が生む”緩やかなつながり”は次世代技術への道しるべ

特許権という言葉は、どのようなイメージを持たれるのだろうか。経済的な利益をもたらす発明の独占権である特許権は、一般消費者の目線からは「自らの発明の成果を独占するための権利」と捉える印象が強いだろう。しかし和田教授は他者に対する技術の使用を制限する面だけでなく、発明者の研究努力を保護する役割や、ライセンス契約を通じ技術の使用を許諾する役割が重要な側面であると語る。
「特許権は私有の知的財産を勝手に使わせない権利です。一生懸命に畑を耕して肥料を与え育てたとしても、誰の土地か明確でないと他の誰かに取られてしまいますよね。誰かに奪われるのが当たり前になると、誰も何も育てようとしません。新しい特許が生まれるまでには、可能かどうかわからないことに対して様々な努力をし、多くの失敗が生まれます。だからこそ特許には投資の成果を私有財産として保護する仕組みが確立されているのです」
そうして生まれた知的財産である特許権は、企業が権利を活用して利益を上げるためのツールであり、ひいては国際経営活動の基盤となるものだ。一企業が営める経営活動には限界があるもの。和田教授はその限界を超える知的財産権を使った海外進出の方法に、企業間のライセンスがあるという。
「海外への進出を目指しても、現地の人に簡単には技術の使用を許諾(ライセンス)できませんよね。自社の大切なコア技術を模倣改善されたり、技術流出されたりするリスクがあります。技術を権利化した特許だけでなく、外食や流通などサービス業でも、知的財産を生かした海外進出では自社の名前で不適切なサービスを展開されてしまいブランドを毀損されてしまう、といったリスクがあります」
そのようなリスクを認識したうえでライセンス契約が活用される背景には、高度技術を持つ競合企業間に存在する微妙な戦略的関係があるのだという。競合相手だからこそ、互いに必要な重要技術を持っている。それら企業間におけるライセンスの与え合い、いわゆるクロスライセンスが増えている。
自社にとって貴重なノウハウを交換しあうクロスライセンスは、お互いに命綱を握り合う形になる。さぞかし厳しい契約で縛られる関係が推察されるが、知的財産の世界ではむしろ曖昧で緩やかな契約に帰結することも多いという。
「高度な技術契約では、生命保険の契約のように起こりうる全ての可能性を網羅して契約書に書き切るのは不可能です。そのため製品を作る具体的な規格や数量、利用の条件といった形で縛るのではなく、お互いに大切なものを渡し合う、人質の交換のような形で緩やかにつながることで、信頼関係のうえで一緒に何かができるかもしれない、と考えています。この人質交換の考え方は、師匠のオリバー・E・ウイリアムソン教授の考えに基づいています。ハイテク企業がクロスライセンスしているとき、その企業間で関連技術のイノベーションがより活発になる、という実証研究を、私は博士論文として指導を受けながら書きました」
その緩やかなつながりを尊重する姿勢は、知的財産のライセンス契約に留まらず、企業同士の出資関係を通じたつながり方にも現われている。
「大きな企業ほど様々な事業へ多角的に取り組んでいますので、まったく同じ事業を営んでいる企業同士の組み合わせはなかなかありません。そのため『この事業では組みたいね』と双方が思っていても、相手が扱っていない分野のノウハウまでさらけ出したくはないんですよね。
そのため、90年代以降には国際的にハイテクの分野で共同出資による合弁事業が増加しました。ある事業部門だけでノウハウを共有し、お互いの取締役でコントロールする。だけど他の分野は他人のままね、という関係を実現できる。この実証研究は、トロント大学の研究者と共同研究としてまとめ発表しました」
こうした曖昧で限定的な契約、しかし柔軟でイノベーティブな協力関係を実証的に把握するには、「特許引用」が有用なのだそうだ。特許引用は、すでにある特許技術と関係のある新たな特許技術が開発されたとき、それを追跡する手法。技術変革の激しい時代に先んじ、次の世代でも勝ち続けるためには、それぞれの企業が手を結び技術を融通しあう必要がある。そのような企業を超えた技術交流は、特許引用に一部表れる。それを経営学とデータサイエンスの双方を生かし追跡把握する、と和田教授は語る。
「オープンイノベーションという言葉が流行してから、すでに何年も経過しました。今やお互いに大切な技術や知識を出し合わないと勝ち残れない時代に差し掛かっています。しかし、全てをさらけ出してしまうと自社が弱い立場に置かれてしまう。手を結ぶ部分と結ばない部分のせめぎ合いが生まれる中で、合弁やクロスライセンスは緩やかにつながれる契約のひとつの形であるというのが、我々の基本的な位置づけです。そして、こういう見方を一般論として曖昧に述べていても、それは海外で評価される科学的成果になりません。検証可能な仮説に落とし込み、因果関係を意識しながら実証する、という時代に国際的に見れば経営学も変革しました」

新型コロナが明らかにした特許の役割
こうして特許がビジネスにおける重要な役割を担う一方、近年では特許に対する価値観を大きく揺るがす事件が起きた。アメリカのバイデン大統領による、新型コロナウイルスワクチンの特許権放棄の方針表明である。
「知財業界の専門家はひっくり返っていましたね。そんなスタンドプレーしないでくれと」
特許権がビジネスに与える影響は業界や商品によって大きく異なる。中には特許により支えられるといえる業界もあるが、製薬業界はまさにその筆頭である。
「ブロックバスターと呼ばれる、今までに比べて画期的な新薬の開発には一千億円を超える費用がかかりますが、成功確率は大変低いのです。何万という候補物質があっても、動物試験に持ち込むまでにごくわずかになり、動物試験が通っても臨床試験で問題が出て認可が下りないかも、というリスクを負いながら新薬は開発されています。
未来に起こりうる次のパンデミックに対処するためにも、薬を開発する体制と、そこに利益を還元できる仕組みは必要です。ただ、ワクチンや医薬が足りない途上国からみれば、特許で守られているために薬が高くなりすぎ、病気が防げなかったり治療できなかったりする現実があります。存在している薬は使わせろ、と言いたくなるのは、生命の問題ですから切実です。かといって、一生懸命に技術を生み育てた人から安く奪い取れるなら、次の技術世代に取り組む人はどうなるのか。特許は、人の生死も左右する医薬の「開発と利用」対立問題をはらんでいるのです」

恩師の導きにより見出した知的財産への扉
「高校生の頃から経済学的なものに興味がありつつ、法学的なものも面白そうだなと思っていたんです。両方を跨いだ勉強ができないかと思っていたのが高校生、いったん少し明確になってきたのが大学2年生でした」
知的財産権に出会う以前。和田教授は入学した学部にて、「学問体系」の選択でいちど迷いに入ったのだそうだ。悶々とする日々を過ごす和田教授だったが、その時に出会ったのが知的財産の第一人者・中山信弘先生だった。
「学問蓄積の観点で見たときに、経済学部や法学部の先生方が見せた蓄積の深さは大変なものでした。その中でも経済と法の学問分野を跨いだテーマとして知財に魅力を感じ、2年生になってから中山信弘先生の入門的なゼミに入れていただいたんです。何度も何度も直接先生に話を聞きにいきました。先生から見ても当時知財法が面白いという学部学生は少なかったようで、面倒をみていただきました。本当に素晴らしい先生で、今の私の礎をくださったのは中山先生のおかげです。
さらに、知財法のほかにビジネス法の学問の先端に触れさせてくださったのが岩原紳作先生です。ゼミでオリバー・E・ウイリアムソン教授の論稿を紹介してくださり、それが後にカリフォルニア大学バークレー校でウイリアムソン教授に師事を直接受ける機会につながりました。これらの先生方の指導によって、知財法や技術契約、イノベーションの研究を、経営学の一つとして位置づけられました。今の私につながる基礎を築き上げられたのは、先生方との出会いがあってこそです」

大学院を通じた高度専門プロフェッショナルの育成へ
人生を変える恩師との出会いを経て、現在は学習院大学にて教鞭を振るう和田教授。ウイリアムソン教授から学んだ合理性限界を重視した研究を指導する。
ミクロ経済学では、価格が市場で交渉され、競争圧力によって価格が上下する「摩擦のないスムーズな交渉市場」のあり方が仮定されていた。これに対し、ウイリアムソン教授は「人間は合理性に限界がある中で戦略的な存在」と理解。その合理性の制約こそが企業組織の存在理由につながるという考えを説いた。
「現実に起こりうる事象の細部がもつ重要性を説いたのがウイリアムソン教授です。かつての経済学は、ある種現実を無視したモデル化がまかり通っていました。それに対するアンチテーゼがウイリアムソン教授の学風です」
和田教授は、ウイリアムソン教授の視角を「きれいな理論を学んでこそ、理論化の過程で切り捨てられたものの大切さが分かるものの見方」と表現する。その"切り捨てられたもの"は、現実の取引で生まれる摩擦。権利で守られる特許の分野においても、摩擦は往々にして存在するという。
「ウイリアムソン教授は、合理性の限界のほかに、現実取引の不可逆性が取引の摩擦の深刻さを決める一つの鍵だと考えました。知財取引でいうと、技術がライセンス取引されることで、より高い価値を生む人間が活用すると考えられます。技術を生んだ人がもっとも高い経済価値のある利用方法を知っているとは限りませんので。しかし現実では、特許権により知的財産が保護されていたとしても、ライセンス取引にはリスクがあります。発明の詳細や発展可能性が一度相手側に知られてしまうと、取引前の状態に戻すことはできなくなり、ライセンスを与える側にとって脅威となる恐れがあるのです。また特許の使用のみを許諾されたとしても、それに伴うノウハウの提供がなければ特許の価値を十分に活かせないという摩擦があり、ライセンスを買おうとする側にも躊躇が生まれます。
さらに、ライセンス契約の効力が失われたとしても、特許の活用に伴う実物資産への投資を無効にはできない点などを含め、全てを取引前の状態に戻すことは不可能、という問題が知財以外にもたくさんみられます。このような取引の障害となり得る摩擦の解決方法として、ウイリアムソン教授は垂直的統合やジョイント・ベンチャーによる解決の可能性を示唆しました。
こうした企業組織の理解は、過度に単純化したミクロ経済学や市場メカニズムの理論では導き出すことはできません。取引上で生まれる摩擦の解消のために企業組織が存在しているという基本原理を説いたのがウイリアムソン教授なのです。
飛躍に聞こえるかもしれませんが、企業の資金調達が株式によるべきか借入金によるべきか、の本質的な差も、人間の合理性の限界という同じ原理から理解できます。摩擦のない世界では両者の企業価値に差を生まない、という有名な定理があるのですが、それを解く鍵も、ウイリアムソン教授は与えました。私が30年以上前に岩原先生から会社法の教えを受けたときにウイリアムソン教授の著作に触れた、というのは、そこから来ています。知財と企業ガバナンスには、人間は戦略的に工夫しつつ協力し、法的な仕組みを運用している、という共通の根本命題があるのです」
先人の理論と現実問題を理解し、論文にまとめることにこそ、大学院教育の価値があると和田教授は語る。ビジネスの現場で生まれる課題に触れるだけなら大学院教育は不要。課題をより深く、一般原理から理解するときに学問蓄積の意義が生きる。それが高度で専門的なプロフェッショナルになるための基盤。そうだからこそ大学院での学びが必要だという。
「卒業生の中には、大学院での学びがアドバンテージになっているという人も少なくありません。例えば医療系の業界では医者を相手にビジネスを展開しますが、彼らには論文を書き続けるような専門家も多い。そうした人たちの文化を理解し、知識の最先端で起きていることを理解するためには、大学院で学術研究に触れた経験が活きます」
かつてはそうしたプロフェッショナル育成の役割の一部を学部、そして会社が担っていた。しかし昨今の就職事情により、その役割はきびしくなっている。和田教授は「大学院が持つ育成機関としての価値」を再認識して欲しいと語る。
「学生側は数年後に転職する前提で就職活動し、企業側も辞められるかもしれない前提で採用する。一方、ジョブ型という名で職業スキルを重視し多種多様な相手と競争する就職・転職市場が姿を現しつつあります。自分の職業スキルは、自ら目標を立て自ら成長せざるを得ない時代ではないでしょうか。そんな現状である今だからこそ、プロフェッショナル育成の場として大学院を活用して欲しいですね。表面的なスキルはウェブ教材などで頑張れば自己養成できるのですが、人類の知の蓄積は、学部生で学べる範囲より遥かに深く、大学院でなければ体得できない部分はかなりあります」
文部科学省の調査によれば、学士課程修了者の社会科学における大学院進学率はわずか2.5%と低迷。一方、国際的には大学院修了を最低基準とする趨勢に傾いている。
「国連などの国際機関への就職には、大学院修了が最低条件となってきています。これは欧米における育成機関としての大学院の価値が認められている証明といえるでしょう。人材流動がひとつの国に閉じている時代が終わりを迎えた今、日本でも知識集約的な仕事においては、大学院で学術研究に触れたアドバンテージが活きてくるでしょう。
大学院における社会科学の一面では、実践的な問題意識を持った研究が求められます。因果関係を意識しデータに基づいて実証する科学的スキルを私の研究室では重視しており、院生は堂々とした分析成果を出せるようになるでしょう。例えば多国籍企業の企業価値の変化を、個々の技術や発明者の単位から分析できるデータベースやソフトウエアがあり使えるようになります。データサイエンスを使って分析する対象が、目に見える表面的な現象だけではもったいない。経営学や経済学や法学をまたぐような本質的な問題に応用対象をみつけられたとき、そこに一生をかけて追い続けるだけの価値を見出すでしょう。
特許は、経営学・経済学・法学のあらゆる方面から研究される領域である、という点で、企業ガバナンスと似ています。そして、社会科学の中でも特に現場を知ってこそ理解を深められる分野であり、理工系の方が社会科学の面白さを理解する糸口になった例も少なくありません。特許と経営活動の関わり、企業の競争関係や戦略的関係、そして組織や法制度の分析に面白さを感じたなら、ぜひ私の研究室のドアを叩いて欲しいと思います」
| 取材: | 2021年11月11日 |
| インタビュアー・文: | 手塚裕之 |
身分・所属についてはインタビュー日における情報を
記事に反映しています。
取材:2021年11月11日/インタビュアー・文:手塚裕之
身分・所属についてはインタビュー日における情報を記事に反映しています。
 インタビュー
インタビュー