
- プロフィール
- 2014年10月〜2015年3月、独国フンボルト大学にて客員研究員。2015年4月〜9月において同国ルートヴィヒ・マクシミリアン大学にて客員研究員。2017年、東京大学大学院経済学研究科博士後期課程修了(博士<経済学>)、同年明治学院大学の法と経営学研究所研究員を経て、2018年学習院大学経済学部に着任。
時代のうねりを捉え、
ビジネス成功の鍵を見出す。
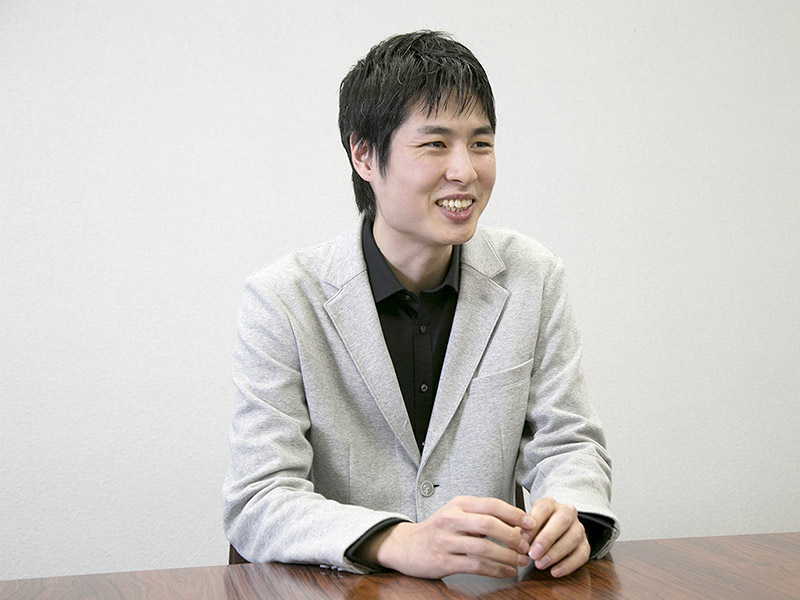
Howを掴む学部生から、Whyを問う研究者へ。
経営史とは、歴史から教訓を学び、今後に活かす学問だ。経営史を学んでいる多くの学生はそう答えることだろう。竹原准教授もその一人だった。学部生の頃、何か事業を興したいと漠然と思っていた。そこで経営史を学ぶことによって、過去の企業家たちが困難に立ち向ったストーリーや、規模を大きくしていったスキル、潰れそうな会社を立ち直らせたハゥツゥ等、そうした経営テクニックの数々を今後のために身につけておこうと考えた。
しかし、それは経営史を学ぶ価値の表層をなぞっていたに過ぎなかった。学んでいくうち、その奥底にある魅力を次第に見出すようになる。それは、轟音とともに物凄い水量で流れ落ちるライン瀑布のように、歴史の奔流に対する「なぜ?」という疑問符を、水煙のように研究者の脳裏へ舞い上がらせるのだ。
「当初は企業家の成功事例から学んでやろうという意識をとても強く持っていました。そこでビジネス界で成功者の多いユダヤ教徒の企業家活動を研究することにしたのです。しかし調べていくうちに、一つの問いが浮かんだのです。『そもそもなぜ、宗教的にマイノリティであるはずのユダヤ教徒が、キリスト教社会であるヨーロッパで経済的に活躍できるようになったのか?』と」
「深く掘り下げていくほど、ビジネスの発展と社会の変化というものが密接に関わっていることが見えてきました。企業家個人の努力ももちろんありますが、その底流には絶えず歴史のうねりがあって、その流れを見出すことのほうが経営史家にとってはより重要だと思うようになり、またそこに研究することの面白さや醍醐味を感じるようになったのです」
大学院に進み、2014年にはベルリンのフンボルト大学、2015年にはミュンヘンのルートヴィヒ・マクシミリアン大学で、それぞれ半年間、客員研究員として留学する。
経営史は海外でどのように研究されており、またどのような研究会が開かれているのかを体感するとともに、現地の研究者と交流を深めた。ミュンヘンでは、ユダヤ教徒の教授のもとに就いた。そこでユダヤ教をアイデンティティとする方々の文化や考え方について触れた。同じ対象を見ていても、自分の見方とユダヤ教徒としての見方は、果たして違うのか、いやそうではないのか。現実に触れ、アタマは整理された。資料は整い、研究は進んでいった。そうして帰国後、矢継ぎ早に論文を公刊する。博士論文では「16〜19世紀ベルリンのユダヤ教徒の企業家精神:ドイツの経済発展と世俗化」を発表した。

今までなかった視点で歴史を俯瞰し、世に問う。
論文の序章には、注目する点として「ユダヤ教徒は宗教的なマイノリティでありながら、なぜ19世紀ベルリンでキリスト教徒と同じように経済的に活躍するようになったか」とある。従来、経済史や経営史の論文や書籍では、ドイツの経済発展を「都市と農村」や「資本家と労働者」といった対立軸で捉えようとしていた。一方、竹原准教授は対立そのものではなく、ユダヤ教徒とキリスト教徒の「経済的な利害関係」の中で捉えていた。
「私は、『ユダヤ教徒とキリスト教徒』という<対立してきた関係>が、どのように変化して経済発展につながっていったか、というところに関して、誰もが納得できる具体的な根拠を示した説明がなされてこなかったと感じたのです」
「たとえばユダヤ教徒がなぜビジネスを上手くやれたかというと、決してテクニックではなかった。これは論文の中で主張してきたことですが、当初ユダヤ教徒は多数派を占めるキリスト教徒と利害対立をしていました。しかし次第に<協力関係>を結んでいくことによって取引できる市場が拡大し、さらに利用できる経営資源がどんどん大きくなり、それに合わせてビジネスもどんどん拡がっていったのですね。すなわち、キリスト教徒との関係を変化させていくことによってビジネスを大きくしていったということです」
「このようなことを歴史という大きな流れから俯瞰して見ると、<世俗化>というキーワードが浮かび上がりました。宗教的な違いというものを、社会が意識しなくなっていく、また経済活動においても気に留めなくなっていく、その歴史の流れの中で、ビジネスが大きくなっていったと私は考えます」

経営史を研究することの他にはない面白さとは?
論文は小説ではない。事実や史実、データに裏打ちされたドキュメントであり、それらファクトに立脚する、今までにはなかった、社会にとって有益な新たなる知見や考察だ。けれども竹原准教授の論文を読んでいると、歴史小説や探偵もののハードカバーを読み進めているかのような気分になる。次はどうなるのかと頁をめくっている。
「まず研究を進めていくうえでコアとなる先行研究を徹底的に読みます。それとは別に一次史料を調べたうえで、人間関係等を細かく見ていきます。事実が揃わないと論文になりません」
しかもその知りたい事実が、何世紀も前の遠い異国での取引関係や協力関係であったりするわけだ。
「ある二人が、ある時期に、同じ会社に所属していたことがわかっても、以前から何らかのコミュニケーションを取っていたうえで大会社となった時に一緒にビジネスを行うようになったのか、たまたま銀行が企業を監督するために送り込まれた人なのか、細かく調べていかないと結論に至らないところがあります。また、しっかりと仮説を立て、その線に沿って史料を探しても、まったくヒットせず、全部外れてしまうことも少なくありません」
「そこに研究の大変さはありますが、調べに調べて事実が見つかり、そうした事実が集まり、そして事実と事実が一つの線で繋がった時、シャベルの先端が金脈にコツンと当たったような快感や醍醐味は正直ありますね」
思うに、経営史学の研究者は、刑事や探偵ではないか。一つの仮説をもとに、文献を探し、耳をそばだて、聞き込みをし、証拠や証言を丹念に拾い集める。一つ一つ検証を行い、裏付けを取り、修正を重ねながら論を整え、そうして真実という名のゴールへと一歩一歩迫っていく。その姿は地道という言葉がふさわしい。地味という言葉でもいい。けれど研究する彼の瞳は、自信と確信に満ちている。その目線の先に見据えているのは、丹念に裏打ちされたただ一つの解だ。
竹原准教授は「大学院ではいかに研究の独自性を出せるか、ということを一つの柱にしたい」という。「経営史学の研究者には、面白そうだから調べてみようと<自分の関心で攻める>タイプと、こういった事実を発見するのだと<社会的使命に燃える>タイプがあります。私は前者でした」
「また研究の過程では、挑戦してみたけれど思っていたことと何か違う……、行き詰まってしまって何も浮かんでこない……、そうした状況が往々にして出てきます。私自身もそうでした。そんな時に『こんなアイデアもある』ということをできるだけ多く投げ込み、院生が良い研究を作り出す手助けをしたいと思います」
「そして、いかに良い論文を書くか、というところに力を入れます。院生時代、私は指導に熱心な先生に恵まれ、そうした先生方から徹底的に赤ペンを入れられ、論文を書く力を鍛えてもらいました。私の院生が論文を書く時にも、かつて自分が指導されたように、一字一句丁寧な添削を心がけていこうと思います」
竹原准教授は、院生とともに学問を究めることを楽しみにしている。「院生とはおそらく世代も近いでしょうし、独自性のある良い論文を書くという同じ目標・同じ目線を持った研究者仲間として、上下関係や師弟関係ではなく、互いに成長を高め合えるような関係性を築けたらと思っています」
| 取材: | 2018年1月15日 |
| インタビュアー・文: | 遠藤和也事務所 |
| 撮影: | 松村健人 |
身分・所属についてはインタビュー日における情報を
記事に反映しています。
取材:2018年1月15日/インタビュアー・文:遠藤和也事務所/撮影:松村健人
身分・所属についてはインタビュー日における情報を記事に反映しています。
 インタビュー
インタビュー