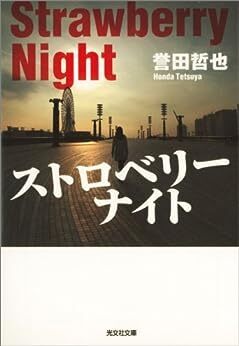
作家の誉田哲也さんは1992年に学習院大学経済学部経営学科を卒業した。『ストロベリーナイト』や『ジウ』などの警察小説で知られているが、一方で10代の若者に向けた青春小説も発表している。そうした小説にどのようなメッセージが込められているのか?誉田さんに聞いた
ー 誉田さんの作品としては『ストロベリーナイト』(光文社)や『ジウ』(中央公論新社)などの警察小説が有名ですが、『武士道シックスティーン』(文藝春秋)や『疾風ガール』(光文社)などの青春小説も10代の読者から支持されています。こうした作品を通じ、若い読者に対してどんなことを伝えたかったのでしょうか?
(誉田)テーマというのは作品によって変わるので一概には言えません。ただよく言うのは、「今じゃないとできないことはない」ということです。
講演をすると、よく「10代のうちに何をやっておくべきか?」という質問を受けるんですが、僕は「それはない」と答えます。今自分ができるのは、目の前にある一つのことだけ。ほとんどその他のことはできない。それは高校でも、大学でも、社会人でも、定年後でも同じことです。逆に言えば、10代のうちにできることは、いくつになってもできることです。そのことを、誰かが10代の子たちに伝えないといけないと思っています。
僕自身、30歳まで音楽で食べていきたいと考えていて、それがうまくいかなかった。それでも今、小説家として仕事ができている。もちろん、インターハイに出場したいとか、18歳の誕生日を理想の彼氏と過ごしたいとか、その時でないとできないことも例外としてありますが、それ以外では一つの挫折でその後の人生が台無しになるなんてことはありません。
ー そうしたメッセージを伝えたいと思ったことが、誉田さんが青春小説を書き始めた動機なのでしょうか?
(誉田)そうですね。そのメッセージを言葉にして言ってしまうと、彼らからすれば「この大人も同じことを言うんだな」で終わってしまいます。でも、小説を通じて伝えれば、主人公と同じプロセスを追いかけることで、納得してもらえると思うんです。それが僕の作品の意味でもあります。
ー 『武士道』シリーズではどんなことを伝えたかったのでしょうか?
(誉田)『武士道』シリーズ3作品でも、メッセージはすべて異なります。
『武士道シックスティーン』のメッセージは、「やるかやらないかは、やる気があるかどうか、好きかどうかでしかない」です。結局なにかをやるための動機は、「やるべき」ではなく、自分が納得できるかどうかです。

香織と早苗という高校の剣道部に籍を置く二人の主人公が、そうした答えに行き着くことによって、読者にもメッセージを納得してもらえるように書いたつもりです。
『武士道セブンティーン』では、前作でタイトルにしていた割に「武士道とはなんぞや」を書きませんでしたので、それをテーマにしています。剣道はスポーツか武術か。武道と暴力の違いは何か。これらは、日本人として、あるべき心のありようを考えることに直結していると思うからです。
最後の『武士道エイティーン』では、彼女たちが18歳の選択の時をいかに迎えるかを描きました。早苗は膝の靭帯を傷めることで、剣道の道を閉ざされてしまいます。
僕はそれをネガティブに受け止めてもらいたくなかった。僕自身が30歳まで音楽を志しながら挫折をして、それが新しい道につながったという経験をしました。そこで、次に何をやるのかという選択肢は過去にしかないということを学んだんです。そういったことを伝えたいと思って書きました。
ー 選択肢は過去にしかないというのはどういうことですか?
自分が過去に何をしてきて、どんなことに喜びを感じたのか。それを振り返ることでしか次の一歩は決められないんです。18年間生きていれば、興味を持ったことは、一つや二つではないはずです。それらの共通点を見いだしていけば、迷った時に選択するためのヒントになると思うんです。
才能というものは難しい。小説家として売れているから才能があるかというと、違うと思うんです。それだと、その人より売れていない小説家は、その人以下の才能しかないことになりますから。
大切なのは、他人がどう思っても、自分はそれを無理なく続けられる、苦痛と思わないで続けられるかどうかだと思うんです。例えて言うなら、日曜日にやっているお父さんの手打ちそばですね。
ー え、手打ちそば……?
(誉田)そう。休みの日に、趣味で手打ちそばを打つお父さんです。本当においしいおそばを食べたいだけなら、何も苦労してそばを打つ必要はない。そば屋さんに行けばいいわけですから。つまり目的が違うんです。お父さんの目的は、そばを打ちたい、できれば家族においしいと言ってほしい、それだけです。

そのためにそばを打つ練習をしたり、そば粉は何割がいいかを研究したりするのは全く苦じゃない。大切なのはそういうことに出合えるかどうか。いくつになっても、それを探す努力を怠らないでほしいんです。
それは『世界でいちばん長い写真』(光文社)に込めたメッセージでもあります。『武士道』シリーズの香織や早苗のように、やりたいことが見つかっている人は幸運ですが、それに出合うことはとても難しい。だからいつ出合ってもいいように、いつもアンテナを張っていてほしいし、出合うために新しい世界に出ることを恐れないでほしい。
ー ではミュージシャンを目指す少女、柏木夏美が主人公の『疾風ガール』(光文社)には、どんなメッセージを込めたのですか?
(誉田)『疾風ガール』は、むしろ才能がある人の話ですね。才能ある人が才能のまま階段を上っていくと、犠牲になる人間が存在してしまう。そのことを意識しておいてほしい。とても残酷だけれど、それを恐れてはいけないし、それを踏まえたうえで、階段を上っていってほしいと思っています。

ー ただ物語はもう一人の主人公である宮原祐司がミュージシャンになる夢をあきらめたところから始まっています。
(誉田)夏美という才能にあふれた少女を、社会がどう見るかの代弁者というのが、彼の重要な役割です。夏美は身勝手で自分のことしか考えていない。だけど、彼女はこれから音楽業界という社会に出ていかなければならない。逆に祐司は夢を諦めて、サラリーマンになるという現実的な選択をすでにしている。そんな祐司だからこそ、夏美のことを客観的に見られるのです。
ー 誉田さんの作品は、読みやすいことも大きな特徴ですね。
(誉田)そこはかなり意識していて、小説としての技術もできるだけありふれたものにしようと思っています。基本的には漢字、カタカナ、ひらがな以外のもので何かを表すのは小説ではないと思うので、「!」や「?」はなるべく使わないようにしているし、「~」みたいな記号もほとんど使わない。カッコは使いますが、会話や引用などを表現するためだけにしか使いません。
それと、読者の「読む」ストレスをできるだけなくしたいと思っています。ルビが入ると視線がブレるので、読んだこともない漢字はなるべく使いません。かといってひらがなばかり続くと読みづらい。なので普段はひらがなで書いている文字を、あえて漢字にしたりもします。主語と述語を入れ替えてみたり、修飾語が二つあったら一つは捨ててみたり。そうやって一文一文の完成度を上げ、読みやすいように努力しています。
ー 10代のうちにやるべきことはないとはいえ、本は読んだほうがいいですよね。
(誉田)そんなこともないですよ(笑)。どのソースから情報を得るのがいいのかは人それぞれだと思っています。映画でこと足りることもあるし、最近はテレビもワンセグがあるから、どこでも見られて利便性が高かったりもします。だから、小説を選ぶ必要があるとも思っていないんです。僕自身、活字が完成形だとも思っていません。
ー それはどういうことですか?
(誉田)僕の小説は、僕がイメージしたものを文章に落とし込み、それを介して読者にイメージしてもらうのが終着点です。読者の脳の中で結ばれた像が動き始めれば、それがその人にとっての完成形になるわけです。だから、僕のイメージと読者のイメージの距離が縮めば縮むほどいい。そう考えると、活字で伝えることのもどかしさも感じます。
先ほど言ったように、僕はとにかく文章を読むというストレスをなくしたい。読者には文章を読んでいること自体を忘れ、可能な限りその作品を疑似体験してほしい。だから小説以上のことをやらないと僕はダメだと思っています。小説が小説であるうちはダメだと思いますね。本当に僕の目指すところを考えたら、映画監督にでもならないといけないのかもしれないけど、それを小説の中でやることに意義があると思っているんです。
ー そうなると、誉田さんが目指しているのはどういった作品ですか?
(誉田)時々、中高生から「私も香織みたいになりたいです」とか、「早苗に会いたいです」と書かれたファンレターをもらいます。そんなふうに、あたかも登場人物がどこかに実在するかのように言われるのが、一番うれしいんです。僕にはファンレターはなくていいし、書いた本に誉田哲也という人間の表現は1行もなくていいと思っています。そういう作品を書いていきたいと思います。