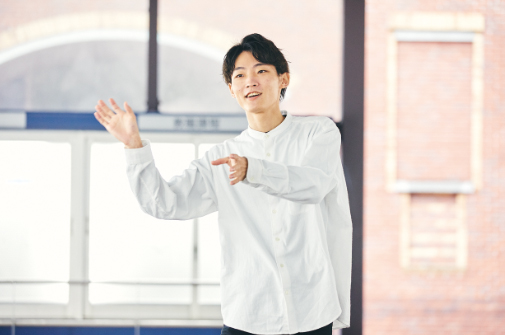社会の経済的な課題を解決するには、まず全体を俯瞰して、状況を正しく知ることが不可欠です。経済学科では市場や政策・制度の役割、為替や物価などの動向を把握する力や、それらの情報をもとに「どこに課題があるのか」と仮説を立てるための知識やノウハウを習得することができます。
2
大きな課題を解決に導くため具体的な戦略を立てる力
経済社会の課題を根本から解決するには、国や自治体レベルの規模感で、人材や予算を動かすことが必要です。経済学科では、こうした政策・制度を立案するための理論やケーススタディ、そしてデータ分析を学びます。それらを他の人に伝える手法も身につけることで、世の中に変革をもたらす実践力を養えます。
3
教養として普段の生活の中でも生きる合理的な思考・判断力
経済学を学ぶことで得られるのは、大きな課題解決のための力だけはありません。日常に起こるさまざまな物事を合理的に洞察し、個々人の人生において、効率よく、実りの多い選択をする判断力も同時に身につきます。これは、社会人にとって身につけるべき基本的なスキルだと言っても、過言ではありません。