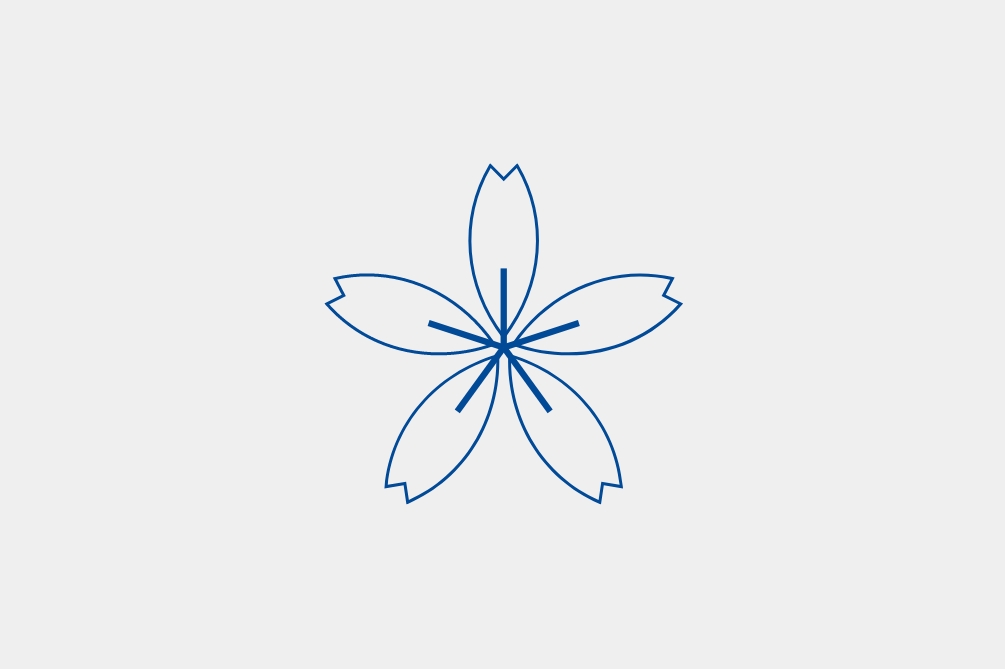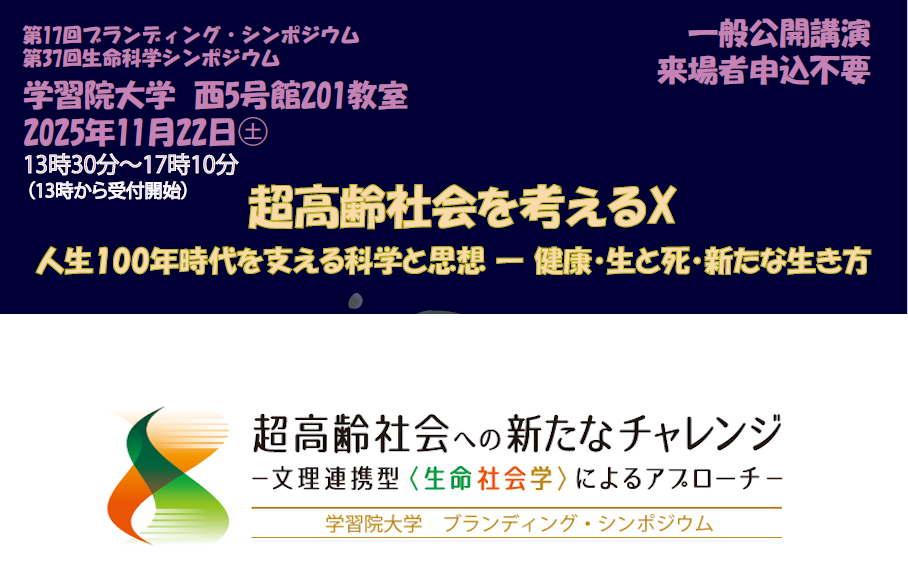文化財だけど教室?!時を超える学び舎ツアー
2025.04.09
社会・地域貢献 未来へ取り組み 教職員
大学生活の大半を過ごし、学生たちの学びや活動、交流の中心となるキャンパス。その特長は大学によってさまざまで、それぞれの個性が光ります。
学習院大学のキャンパスは、都心に立地しながらも、一歩足を踏み入れると、豊かな自然、歴史・伝統ある建物、最新鋭の建物が見事に調和し、都会の喧騒を忘れさせるような心地よい空間が広がります。
そのキャンパスを維持し、学業に専念できる環境を守り・作り続けているのが、学習院施設部施設課の職員たちです。
今回は施設課建築担当職員の政清さんと栗原さんに、本学の特長の一つ、今も現役として使用されている「国登録有形文化財 ※1」を中心に、魅力溢れる目白キャンパスを案内してもらいます!
ぜひキャンパスマップを見ながら、それぞれの建造物を辿っている気持ちでお読みください。(キャンパスマップはこちら)
※1 国登録有形文化財...建造物、工芸品、彫刻、書跡などの有形の文化的所産で、日本にとって歴史上、芸術上、学術上価値の高いものを総称して「有形文化財」と呼ばれ、そのうち国が登録する登録有形文化財(建造物)は、近年の国土開発や都市計画の進展、生活様式の変化等により、社会的評価を受けるまもなく消滅の危機に晒されている近代等の文化財建造物を、後世に幅広く継承していくために作られた制度です。建造物の国登録有形文化財は、原則、築50年以上が経過し、①国土の歴史的景観に寄与しているもの、②造形の規範となっているもの、③再現することが容易でないものである必要があります。
引用:文化庁公式ウェブサイト
四季折々の風情あるキャンパスと歴史を感じる7つの「国登録有形文化財」




政清(以下、政):皆さんは、学習院大学にお越しになったことはありますか?たくさんの木々や草花に囲まれ、季節の移ろいを感じることができる、大学というより自然公園にいるかのようですよ。
栗原(以下、栗):特に東京都心には、まるでオフィスと見まがうビル型のキャンパスも多いのですが、本学は思わず東京の真ん中にいることを忘れてしまうほどですよね。
政:そんな目白キャンパスを語るのに欠かせないのが、明治から昭和に竣工した歴史的建造物です。学習院には全部で7つの「国登録有形文化財(以下、有形文化財)」があります。
栗:今日は私たちが皆さんをご案内しましょう。 普段は見ることができない建物内などもお見せできたらと思います。東京メトロ副都心線 雑司が谷駅から近い「正門」からスタートです。

学習院ならではの文化財〜
正門、東別館(旧皇族寮)、北別館(旧図書館)、乃木館(旧総寮部)、厩舎



栗:「正門」から入ると「東別館」や「北別館」など、学習院の長い歴史を感じさせる建物に出合えます。これらはいずれも有形文化財です。
政: どれも現役の建造物として使用するため、建物は耐震補強を行いましたが、現存数の少ない明治から大正期に建築された学校寄宿舎である「東別館」には、同じ時代に製造された「大正ガラス ※2」が今もそのまま窓に使用されていたり、旧図書館であった「北別館」には各所に学習院の校章である桜のモチーフが散りばめられていたりと、いずれも特徴的な意匠などが多く、改修をする際には、お寺や神社の修理を得意とする大工さんや左官屋さんにもに携わってもらいました。
※2 大正ガラス...一枚一枚手作りがゆえ表面の平滑度が落ちるため、ガラス越しの景色が曲がって見えるのが特徴。
政:教室ではありませんが、「乃木館(旧総寮部)」、「厩舎」も有形文化財に登録されています。いずれも明治から昭和に竣工した歴史を持つ建物です。
栗:厩舎は中通路を設けるプランが、軍隊の形式を継承したともいわれています。現在は馬術部の活動拠点となり、当時から変わらず、今も心地よい蹄の音が響き渡ります。


英国の名門イートン校がモデルの「西1号館(旧中等科教場)」

政:正門を背に直進すると、右側に見えて来るのが「西1号館(旧中等科教場)」で、この建物も有形文化財です。昭和5(1930)年に中等科教場として竣工しました。およそ100年前になりますね。「ネオ・ゴシック様式 ※3」の外観と「アール・デコ ※4」要素が散りばめられた内観が特徴の建物です。
栗:実は西1号館の屋上には、空調機が乗っているのですが、平成21(2009)年の有形文化財の認定の際に、外観を損なうという指摘を受けました。しかしルーバー(目隠し)をしていますし、そこは学習環境を守るために移設は譲れないとそのままにしています。文化財としての価値と学びの環境のバランスを取るのも難しいですね。
※3 ネオゴシック様式...中世ゴシック建築の復興を目指す動きの様式。
引用:大阪文化財ナビウェブサイト
※4 アール・デコ...1910年代から30年代にかけてフランスを中心にヨーロッパを席巻した工芸・建築・絵画・ファッションなど全ての分野に波及した装飾様式の総称。直線と立体の知的な構成と、幾何学的模様の装飾をもつスタイル。
引用:東京庭園美術館ウェブサイト


ヨーロッパの古城を思わせる「南1号館(旧理科特別教場)」

栗:西1号館と共に広場に面するのが、南1号館(旧理科特別教場)です。中世ヨーロッパのお城みたいですよね?元々は昭和2(1927)年に、中等科・高等科の理科特別教場として竣工しました。昭和24(1949)年大学理学部開設に伴い理学部研究棟となりましたが、現在は演習などの授業で使用されています。
南1号館も有形文化財ですが、現役の「教室」でもあります。
政:本学の有形文化財の中では直近に改修をした建物ですので、そのエピソードをご紹介しましょう。平成23年(2011)3月に起きた東日本大震災を受け、南1号館に被害はなかったものの、改修にあたり、昭和初期の建物として、コンクリートの壁の調査を基準の2倍行ったにもかかわらず、工事を進める過程で想定外のことが次々明らかに...。
栗:あれは本当に大変でしたね。例えば、建設当時のコンクリートは、現場で人力で練っていたこともあり、砂利とコンクリートが適切に混ざっておらず、これをジャンカというのですが、時間が経つと砂利が浮き出てしまうんです。当時はそのような方法を採っていましたが、現代では施工不良といえますね。
政:これも壁のタイルを剝がしたときに始めて気づきました。工事前の調査で確認した箇所は全て問題なかったので、全く想定外だったのですが、放置することはあり得ません。気づけて本当に良かったのですが、また一からタイルを剥がして確認して...
そこで調査と耐震補強設計を見直すべく、一旦、工事を中断せざるを得ない状況になりました。しかし目標の1年後の4月には間に合わないことは明白。次は教室数の確保のため、南1号館に代わる教室として、南2号館を緊急的に改修することになりました。それも急ピッチで終え、なんとか4月の授業には間に合いましたし、南1号館は当初の計画から1年遅れではあるものの無事に完成しました。
栗:古い建造物に現代の基準で耐震工事を施すこと自体難しいのですが、文化財としての価値に影響を及ぼさないようにしながら、地震に耐えうる強度にしなければならない。でも授業開始は待ってくれない...思い出すだけでドキドキしてきます...
政:あとは教室として使用する以上は、バリアフリーへの対応も必要です。手続き上、エレベーターを付けることが難しかったので、「エレベーター棟」として2つの建物を並べることでクリアしました。ここにも仕掛けがありまして、ヨーロッパ発祥の「ネオ・バロック様式 ※5」の建物ですので、1階(地上階)のボタンが「G」(イギリス英語でGround floor)で、ヨーロッパ式の表記にしています。
※5 ネオ・バロック様式...欧州の19世紀後半期に見られる芸術の一傾向で、バロック的な動感豊かな表現を目指すもの。建築の代表例では、C.ガルニエによるパリのオペラ座(1861~75)などがある。
引用:大阪文化財ナビウェブサイト
栗:内装も当時の趣向を残すようこだわりました。階段の手すりのデザインはアール・デコ調の「G」(Gakushuinの頭文字から取られたデザイン)を残して、現代の規格に合ったガラス手すりを付加したり、手すりの支柱もゴシック調で珍しいデザインですので、そのまま活かしたり。また理学部研究棟時代には木質の床の上に長尺シートという塩ビ製のシートを貼っていたのですが、化学実験室の復元教室(202教室)を作るにあたり、竣工当時の床を再現すべく、使える床板を集めて敷き詰めました。白基調の建物内や廊下のデザインも当時のまま、現代の素材で再現したものなんですよ。
政:ほかにも、竣工時の窓枠はスチールのドーム型だったところ、当時の写真を見ながらアルミで再現。トイレは現代に合わせて綺麗に作り直していますが、TOTO前身の「東洋陶器株式会社」の実験用流しも手洗いとして復元教室の前に設置しています。

栗:歴史的に貴重な設備としては、化学実験などで発生するガスを排気する設備の「ドラフトチャンバー」も実験室時代の遺構として残しています。平成31(2019)年3月には、化学遺産としても認定を受けました。
有形文化財でありながら、教育施設であるというのは、維持するのはとても大変なのですが、他にはない、魅力の一つでもありますね。



今はなき大学のシンボル「ピラミッド校舎」~現在はパワースポットとして

栗:最後に少し寄り道を...西1号館と南1号館にある三角のオブジェです。有形文化財ではありませんが、本学のシンボルとして、昭和35(1960)年竣工から50年近く愛された「中央教室」、通称ピラミッド校舎という建物がありました。平成20(2008)年に中央教育研究棟の建設と共に取り壊されましたが、校舎の頭頂部をオブジェとして残しました。
政:そのためこの広場は「ピラミッド広場」とも呼ばれています。そしてまことしやかに噂される、学習院のパワースポットでもありますので、ぜひ皆さんも"てっぺん"に手をかざしてみましょう。

学習院の歴史そのものを体現する佇まい
栗:ここまで7つの有形文化財を見ていただきましたが、いかがでしたでしょうか?いずれも現役の建造物です。長い学習院の歴史の中で、多くの学生さんたちが学び過ごしてきました。
政:有形文化財ですから、大切に扱わねばならないのは当然ですが、目白キャンパスに残るこれらは学習院の歴史そのものです。平成21(2009)年に有形文化財として登録されて以降、震災を経ても深刻なダメージもありません。その佇まいはそれぞれ学習院らしさを体現していると感じています。そして、南1号館の耐震工事のように、歴史ある貴重な建造物を保存していくことは、技術的な難しさはもちろん、非常に手間のかかることではあります。しかし一度失ってしまったら再現が困難なほどに貴重であるからこそ、現役の建物として、保存・使用していくことは、本院ひいては目白地域の資産を守り、それぞれの時代の特色を継承していく、とても意義あることと思っています。
栗:歴史的な建造物は、博物館のように見学のためだけの建物になりがちですが、本学では当時の趣を残しつつ、時代に合わせて進化し続ける教室で学びを享受できる、そういう貴重な体験を学生さんたちにはぜひ味わって欲しいと思っています。
政:そしてこれらの歴史ある建物たちのオーセンティシティ(真実性)を維持しながら、新しい建物に連続性を持たせるようにしています。こんな魅力あるキャンパスで充実したキャンパスライフを送ってもらいたい、その強い想いから、日々全力でキャンパス整備に取り組んでいます。