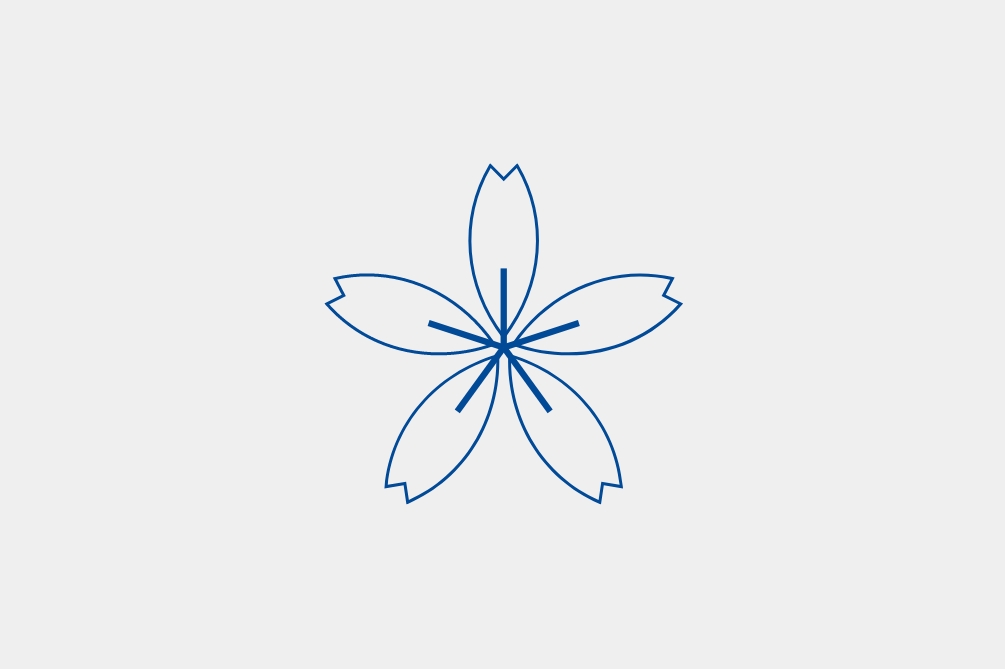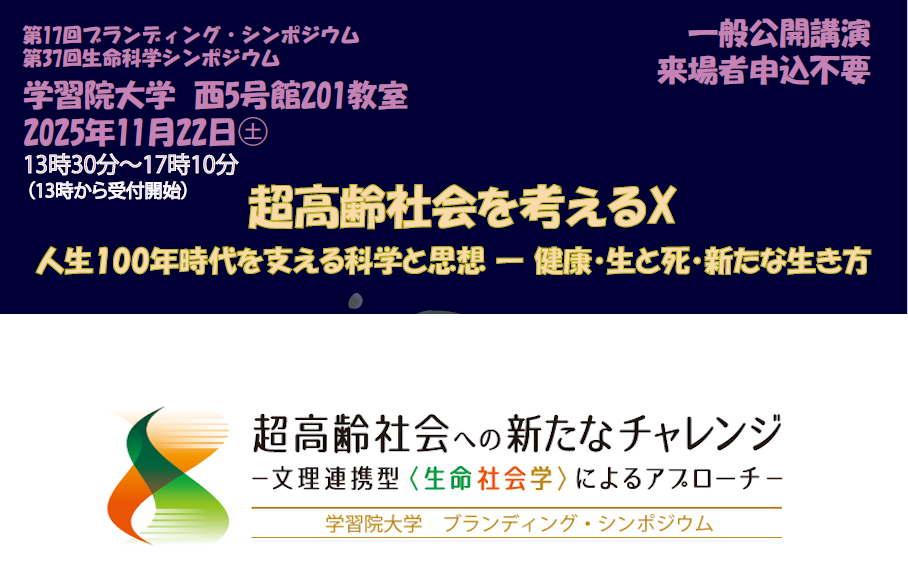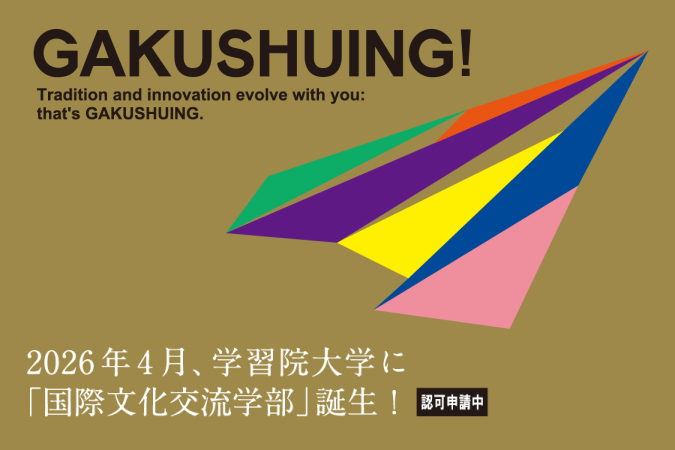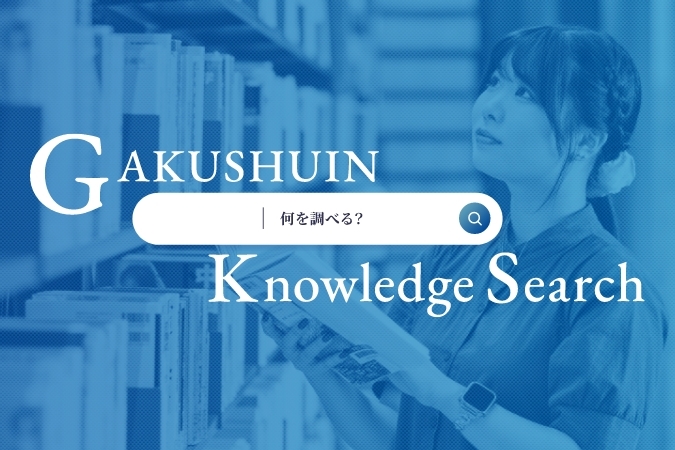学長メッセージAbout Us

ようこそ学習院大学へ
学習院大学は、明治10(1877)年に華族の学校として出発し、明治17(1884)年に宮内省所管の官立学校となった「学習院」を母体に、昭和24(1949)年に私立の新制大学として開学しました。令和6(2024)年には大学創立75周年を迎えましたが、国立から私立に転換した極めて珍しい発展過程をもつ大学です。現在は5学部17学科と大学院6研究科と法科大学院で構成され、大規模な大学ではありませんが、これまでに多くの社会に貢献する「人財」を育成してきました。
輝かしい未来を期待した21世紀でしたが、四半世紀を過ぎようとする現在、少子高齢化の進展や人口減少、経済成長の鈍化や経済格差の拡大、温暖化・環境問題の高まり、新興感染症のまん延、戦争の勃発、大地震などの大規模災害の不安、生成AIの登場など、私たちの社会の不確実性は大きく高まっています。このような時代を生きるには、変化の予兆を機敏に感じ取る感性や予想しない変化に対応できる柔軟性・強靭性を身につけることが大切です。
学習院大学は、学界や社会で高い評価を受けている教授陣による少人数教育が行われ、それぞれの専門教育には定評があります。一方で、不確実性の高い時代には、専門にとらわれずに視野を広く持つことも必要です。そのため、所属する学部の授業だけでなく、関心に応じて選択できる「全学共通科目」を充実させています。その中には「生命社会学」や「宇宙利用論」など文系、理系の枠を超えた学際的な科目もあります。また、「データサイエンス」をはじめ3つの分野において「副専攻制度」を用意しており、自分の専攻に加えて特定のテーマを追求することができます。
学習院大学では、このようにそれぞれの専門を深めるとともに、より広い領域の学際的な学びを実現することができます。
学習院大学は、これからも時代を創る「人財」を養成すべく改革を進めていきます。

学習院大学長 遠藤 久夫
学長告辞
令和6年度 大学院、専門職大学院修了式及び大学卒業式
学習院大学の卒業生のみなさん、大学院の修了生のみなさん、卒業、修了おめでとうございます。心よりお祝い申し上げます。
本年度の卒業生は、法学部・経済学部・文学部・理学部・国際社会科学部の5学部あわせて2,001名です。大学院の博士前期課程の修了生は、6研究科あわせて111名、博士後期課程に在籍中に博士の学位を授与され課程博士になられた方が8名、法科大学院を修了された方が20名です。すべての卒業生、修了生のみなさん、おめでとうございます。
また、ご父母の皆様、ご家族の皆様もさぞお慶びのことと存じます。
ここに耀英一学習院長、諸戸清郎桜友会長をはじめ、来賓の皆様のご臨席を賜わるなかで卒業式・修了式を挙行できますこと、たいへんうれしく思います。
さて、皆さんは学習院大学、大学院で専門分野を学ばれ、四月からそれぞれに新たな道を進まれるわけですが、皆さんを待ち受けるのはどのような未来なのでしょうか。一言でいえば、予想ができない、不確実性が非常に高い未来だと思います。もちろん、先のことは分かりませんから、いつの時代でも「未来は不確実」なものです。しかし、今、われわれの眼前にある未来はこれまでになく先が見通せない時代だと思います。
大学を卒業される皆さんは、入学したときには、新型コロナウィルスの影響で、半数近くの授業が遠隔授業でした。このようにオンラインで大学の授業を受けるなどということを、中学生のころに想像できたでしょうか。このように現代は、先が読めない時代なのです。
今後、不確実性が高くなるという要因は容易に見つけることができます。たとえば、日本の少子高齢化はますます進んでいきます。皆さんが60歳代後半になっている今から45年後の2070年には、65歳以上の人口は全人口の約4割となり、75歳以上の人口は全人口の4分の1になると予測されています。このような日本人の5人に2人が65歳以上、4人に1人が75歳以上という社会はどのような社会なのか想像もつきません。現在でも日本の高齢化率は世界一の水準ですから、このような超高齢社会を経験した国はどこにもありません。どんな社会になるのか予想できません。
テクノロジーの進歩も未来の不確実性を高めます。約30年前にインターネットの商業利用が開始されました。インターネットはコミュニケーションの在り方の変化を通じて、仕事の方法、ビジネス、産業、教育、政治、マスコミ、娯楽など極めて広い分野に変革をもたらしました。しかし、AI技術、とりわけ最近注目されている「生成AI」がもたらす社会変革はインターネットの比ではないと思います。インターネットはしょせん通信手段の新しい技術にすぎません。それでもこれだけの変革をもたらしました。しかし、生成AIはコンテンツ自体の創造に関わるのですから、人間の知的活動に匹敵するものです。したがって、その社会変革のエネルギーの大きさはインターネットの普及による影響をはるかに超えるでしょう。
さらに、かつては経済大国と言われた日本ですが、バブル崩壊以降、経済成長は低迷しており、1968年から42年間、日本は世界第二の経済大国でしたが、現在は第4位にまでランクを下げました。成長軌道になかなか乗れず、人口減少、少子高齢化が進む日本の経済はどうなっていくのでしょうか。また、ロシア・ウクライナ戦争の先行きは不透明ですし、日本を取り巻く安全保障環境も厳しいものがあります。南海トラフ地震や首都直下型地震などの巨大災害の発生も高い確率で予測されています。
このように、皮肉なことに、「未来の不確実性はこれまでになく高い」という予測の「確実性」は非常に高いのです。
それでは、そのような未来に生きることになる皆さんはどう生きていけばよいのでしょうか。そのことについてお話ししたいと思います。
学習院には教育目標があります。それは「ひろい視野」「たくましい創造力」、「ゆたかな感受性」をもった人を育てるというものです。「ひろい視野」「たくましい創造力」、「ゆたかな感受性」といってもその具体的な解釈は人さまざまだと思いますが、私なりの解釈で、この目標が、不確実性の高い未来に生きる皆さんにとってたいへん役に立つメッセージであることをお話ししたいと思います。
「ひろい視野」とは、グローバルな視点、外国の事情を理解するというイメージがありますが、もちろん、それだけではありません。高齢者など年齢の異なる世代の考え方の理解や異性の考え方の理解、健康を損ねた人や障害を持つ人のおかれている立場の理解、都会と地方の生活の違いの理解など、幅広いものです。すなわち「広い視野」とは「多様性の理解」を意味します。今日の社会は様々な要素が複雑に絡みあって形成されています。多様性を理解しなければ、視野が狭まり物事の本質が見えません。
学習院の教育目標は、次に「たくましい創造力」と続きます。しかし、私は、3番目の「ゆたかな感受性」が「ひろい視野」に続くべきだと思います。「ひろい視野」で多様な情報にアクセスして多様性を理解したとしても、それだけでは十分ではありません。そのままではただのバーチャルな情報でしかありません。それらは所詮「他人事」なのです。見たものを深く理解し「共感する」ことによって、はじめて、バーチャルな「他人事」が、自分とかかわりのある事、すなわち「我がこと」としてとらえることができるのです。「我がこと」としてとらえられることにより、はじめて自分自身の行動や選択の参考となるのです。そしてそのことは自分自身の成長にもつながります。「他人事」を「我がこと」としてとらえることに必要な力が「共感力」なのです。すなわち、教育目標である「ゆたかな感受性」というのは「豊かな共感力」のことをいうのだと思います。
インターネットやAIの普及によりさまざまな情報へのアクセスは極めて容易になりました。しかし、その情報が「我が事」としてとらえられなくては我々の行動に何の影響も与えません。それゆえに「感受性」すなわち「共感力」は非常に重要なのです。
つぎの教育目標は「たくましい創造力」です。何か創造力というと大仰に聞こえます。研究者でも芸術家でもない自分には創造力など無縁だと思われる人も多いかもしれません。しかし、ここでいう創造力というのは、前例がなく、不確実性の高い社会において、自分の人生を切り開いていく能力だと思います。広い視野で様々なことを「我がこと」としてとらえ、それを基本に人生を切り開く力です。前例がないのですから自身の道は自ら創造していくしかありません。それがたくましい創造力の意味ではないでしょうか。
いままでのことをまとめれば、「幅広い視野で世の中を見て、それをただの情報にとどめず、我がこととして認識して、それを基礎に、果敢に自身の将来を築いていくこと」、このために必要な力が、学習院の教育目標である、「ひろい視野」「ゆたかな感受性」「たくましい創造力」なのだと思います。
しかし、それだけでは十分ではありません。不足しているものがあります。それを一つつけ加えたいと思います。それは「しなやかな強靭性」です。皆さんがこれから生きていく不確実性の高い社会には困難な課題も多いと思います。したがって、挫折や困難から立ち直る精神的な強さが必要です。強さといっても困難に頑強さで対峙するのではなく、柳の枝のようにしなやかに復元する柔軟性に富んだ対応力です。このような力は、広い視野で物事を把握し、それを豊かな共感力で「わが事」としてとらえる習慣があれば身に着けることができます。このような習慣があれば、たとえ困難に陥っても、視野狭窄に陥って行き詰まることなく、「まだまだ選択肢が十分ある」と、柔軟な対応ができるのではないでしょうか。
「ひろい視野」「ゆたかな感受性」「たくましい創造力」「しなやかな強靭性」という学習院の教育目標に一つを加えた四つの言葉をもって、皆さんが「充実した未来」を送ることができますよう、エールの言葉といたします。
本日はおめでとうございます。
令和7年3月20日 学習院大学長 遠藤久夫
令和7年度 大学院、専門職大学院及び大学入学式
新入生の皆さん、入学おめでとうございます。学習院大学を代表して心より歓迎いたします。また、皆さんを長年にわたり温かく支えてこられたご家族や関係者の皆さま方に、心よりお祝いを申し上げます。
本年度の新入生は、学部は5つの学部をあわせて2,215名です。大学院は6つの研究科と法科大学院をあわせて157名です。新入生の皆さんを迎え、耀 英一学習院長、卒業生の同窓会である桜友会の諸戸 清郎会長、父母会をはじめとして、来賓の皆様のご臨席を賜わるなかで入学式を挙行できますこと、たいへん嬉しく思います。
皆さんの胸には、希望と期待、そして少しの不安が入り混じった、特別な感情が溢れていることでしょう。皆さんがこれから学ぶことになる学習院大学について少しお話しします。
学習院大学は、明治10年に「華族学校」として出発し、明治17年に宮内省所管の官立学校となった「学習院」を母体として、終戦後の昭和24年に私立の新制大学として新たに開学したものです。国立の学校から私学に転換したのは、わが国ではおそらく唯一ではないかと思います。
新制大学になって昨年は75周年を迎えました。当初は2学部で発足しましたが、着実に発展し、現在は5学部17学科と大学院6研究科と法科大学院で構成される総合大学となり、これまで様々な領域で、社会に貢献する人材を育成してきました。
最近の動向としましては、おととしの4月に新図書館を中心とした東1号館が完成しました。図書館だけでなく、皆さんが学習する上で最新の環境を提供しており、多くの学生の皆さんが集い、知的交流を行う新たな拠点となっていますので、皆さんも積極的に活用してください。
また、先月には著名な建築家である前川國男氏の設計による旧大学図書館を大規模に改修し、「霞会館記念学習院ミュージアム」として開館いたしました。これは大学博物館としては大規模な収蔵設備を持ち、学芸員養成の質的向上や文化財の公開による地域貢献など、多くのことが期待されています。また来年度を目途に学習院女子大学を統合して、学習院大学の新たな学部として発展させていく計画が進んでいます。
学習院大学は、これからも時代の要請に応えるべくソフト、ハードの両面で前進していきます。本日から皆さんは、この学習院大学の研究・教育をさらに発展させ、新たな学習院大学の歴史を作っていく大切なパートナーとなりました。我々は、そのことを、たいへん心強く思っています。どうぞ、このような学習院大学で充実した大学生生活が送れることを期待しております。
ここには学部に入学された方と、大学院に入学された方がおられます。まず学部に入学された皆さんに申し上げます。本日、皆さんは大学生という新たな立場を得ると同時に、かけがえのない4年間という「時間」を与えられました。時間は誰にも平等に与えられた貴重な資源です。とりわけ、この大学生の4年間という時間はとても貴重です。大学は、様々な学問や価値観に触れることができる場所です。講義やゼミ、課外活動などを通じて、自分の興味や才能を発見し、深く掘り下げることで、将来のキャリアに繋げることができます。また、多くの人々との出会いを通じて、多様な考え方や価値観に触れ、視野を広げることができます。
このようにこの4年間は実に貴重な期間だといえます。そこで、皆さんには二つのことをアドバイスしたいと思います。
第一に、勉強であれ、課外活動であれ積極的に取り組んでください。情報が溢れる現代社会では、与えられた情報を鵜呑みにするのではなく、自ら考え、判断する力が求められます。大学の授業は高校までの授業と大きく異なる点があります。それは、それぞれの分野に一生かけて取り組んでいる先生が教えているということです。したがって、授業の内容の背後には非常に深いものがあります。高学年になってゼミナールや研究室に所属するようになると、そのことはよくわかります。ですから、ただ授業を聞いているだけでは、あまりにももったいないのです。自ら積極的に取り組んでこそ、その奥深さが実感でき、批判的思考力や問題解決能力を磨くことができるのです。是非、大学での学びを通じて主体的に行動できる人になってください。
積極的にかかわっていただきたいのは勉強だけではありません。課外活動にも積極的にかかわっていただきたい。自分一人だけでは自己実現や社会への貢献は実現しません。現代社会では、多様な価値観を持つ人々と協力し、共に課題を解決していく力が不可欠です。大学は、多様な背景を持つ人々が集まる場所です。課外活動や授業やゼミなどで友人との交流を通して、積極的にコミュニケーションを取り、互いを尊重し、協力し合うことを通じて、自己実現はもとより、より良い社会の実現に貢献できる人になっていただきたいと思います。
アドバイスの二つ目は、広い視野を持っていただきたいということです。現在は複雑な社会ですから、表面的な様相だけでは変化の本質はとらえられません。そのため、視野を広く持つことが本当に重要です。大学では、専門分野の知識を深めるだけでなく、広い視野で物事を捉える力を養ってほしいと願っています。多様性を理解し、他者の立場に立って共感することで、初めて見えてくる世界があります。知識を得るだけでなく、深い洞察力、共感力も身につけてください。
そのためには課外活動などで様々な人と交流することも重要ですが、学習院大学では、それぞれの専門を深めるとともに、より視野の広い学際的な学びができるような教育上の仕組みも整えています。
その一つが、自分の専攻する分野以外のことが学べる、「全学共通科目」を豊富に用意していることです。その中には理系の先生と文系の先生が同じテーマで講義する、文系、理系の枠を超えた「文理融合科目」もあります。
また別の仕組みとして「副専攻制度」があります。これは、自分の専攻に加えて特定のテーマを追求することができる制度で、現在「データサイエンス」をはじめ3つの分野の副専攻が認められています。たとえば、文学部の学生が「データサイエンス」を副専攻として、ご自身の専門以外にデータ分析の勉強をする、などということができます。
加えて、現代は、グローバルな視点を持つことは避けられません。本学は、短期・長期の留学制度をはじめ、様々な国際化のプログラムを用意しています。おととしのデータになりますが、540名の学生がこの制度を使って海外で勉強しています。これは本学の学生の17名に1人が海外で勉強していることになります。
このように、学習院大学は、専門を深めつつ、視野を広めることのできる仕組み、グローバル化に対応する仕組みを整えています。せっかく用意してあるプログラムです。広い視野を持つために是非活用してください。
皆さんは「大学生という時間」と「学習院大学という場所」が与えられました。しかし、これらは、演劇に例えるなら、舞台や装置にすぎません。主役を演ずるのは皆さんです。4年間は本当にあっという間です。どうぞ学習院大学という魅力的な環境を大いに活用して、充実した大学生活を送ってください。
次に大学院に入学された皆さんに申し上げます。皆さんは学部での勉強を通じて、学問の面白さ、奥深さに触れ、大学院でより専門を深め、研究者やプロフェッションを目指したいという志を持った方たちだと思います。私たちの直面する社会は多くの課題を抱えています。これらの課題を解決する上で、人間がこれまで蓄積してきた知識、すなわち学問を活用することは非常に有効です。皆さんはそれを学ぶことにより、それぞれに、難しい課題を解決することに貢献することになるのだと思います。
学習院大学には、高い研究力に裏付けられた研究志向の風土があります。たとえば、国の研究に対する補助金である「科研費」の採択率は、令和3年度から令和5年度までの3年間連続で、私立大学中、第1位、令和6年度は第2位という実績があります。
また令和6年度には、優れた研究を行っている大学院生を顕彰する「日本学術振興会育志賞」を本学の大学院生が受賞しました。この受賞はたいへんな快挙で、今回は全国の大学等から推薦された177名の中から19名が選ばれました。このうち、私立大学は本学を含めて2校しかなく、他は旧帝大をはじめとする有名国立大学でした。
これらの事実は本学の研究力の高さを示すものです。学問の道は決して楽ではありませんが、学習院大学大学院の高い学問的風土の下で、志ある皆さんが充実した学究生活が送れるよう心から願っています。
大学に入学した皆さんが、また、大学院に入学した皆さんが、それぞれに目的を遂げられて、数年後の卒業式や修了式を輝かしい笑顔で迎えることができますよう、心より祈念してお祝いのことばといたします。
令和7年4月3日 学習院大学長 遠藤 久夫
Recommend