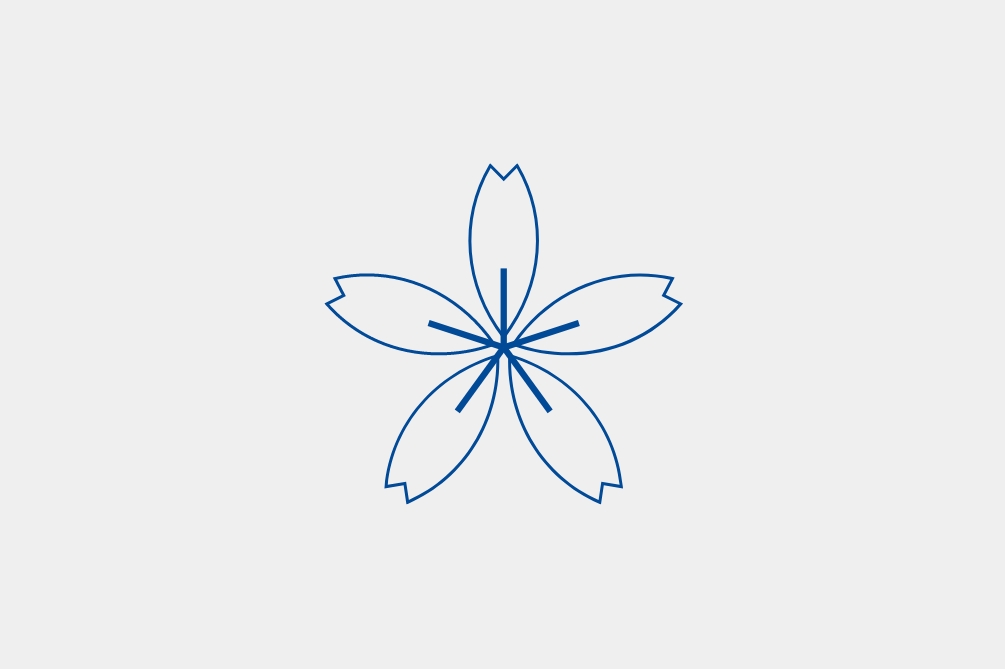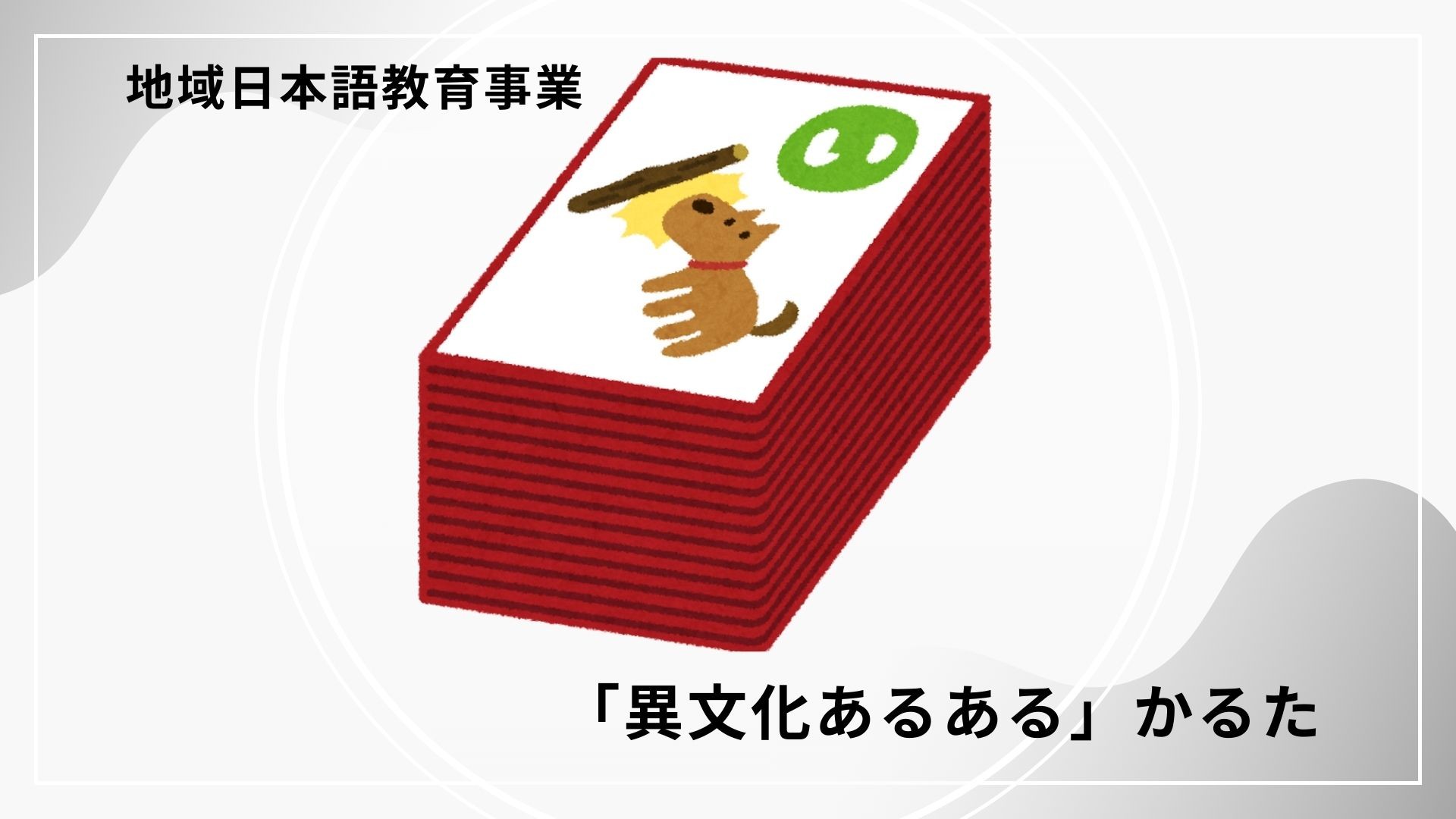【開学75周年企画】あのころ ― 第1回「女子学生の登場 」
桑尾 光太郎 (学習院アーカイブズ)
2024.03.01
シリーズ 教職員
令和6(2024)年、学習院大学は開学75周年を迎えます。
「あのころ」は、学習院大学の歴史を通して戦後日本の高等教育の一端を振り返るコラムです。
学習院大学が開学した1949(昭和24)年、在籍学生358名のうち女子は1年生6名・2年生1名の計7名でした。それまで男子しかいなかったキャンパスに現れた女子学生の声を、同年に創刊された『学習院新聞』は次のように伝えています。
記者「御入学おめでたうございます、まづ皆様が一番最初にお感じになつたことは」
A「教室の汚いのに閉口しました」(略)
C「一般に非衛生なのに驚きました、まるで私達掃除婦と同義語ね」
一同「うなづく」
記者「それは御気の毒で、では男子の学生に関してお気付きの点は御座いませんか」
B「教室内では禁煙して頂きたいと思います」
A「窓とは随分敷居の高い出入口だということを発見しました」
C「それに机や椅子はまるで踏台と同じよ」
(「新女子大学生と一問一答」『学習院新聞』2号 1949年6月27日)

その後、1950年代半ば(昭和30年代)過ぎから4年制大学を志願する女子が急増し、その大部分が文学部に入学しました。とくに都心の私立大学に女子が集中し、学習院大学文学部の場合、1960年代から女子の比率は80%以上を占め、政経学部と理学部をあわせた大学全体の男女比は約7:3となりました。学習院と同様に立教大学や青山学院大学の文学部なども、女子が入学者の8割を占めるようになります。
当時の新聞は、キャンパスの変わり様を次のように伝えています。記事は男目線で書かれているので割り引いて読む必要がありますが、それまで学生服の男子が大多数だったキャンパスを華やかな雰囲気にしたことは想像に難くありません。

女子学生を迎えて、大学の空気はたしかに変った。まず目につく色彩のはなやかなこと。色とりどりのセーターが学内をデモる。足もとはハイヒール、クツ下はシームレス、マニキュアもいまは常識らしい。休み時間には、服飾雑誌をかこんでおしゃれ話がはずむ、といったあんばい。彼女たちの服装は、つまり教室向きというより銀座、新宿向きなのだ、と男子学生は解説する。しかし、この解説を裏返すと、大学もやっと風通しがよくなり、社会の中の大学になりつつあるともいえそうだ。
(『朝日新聞』 1962年11月13日)
とはいえ、学習院大学を卒業した女子の就職率は昭和30年代を通して20%前後で、80%を超えていた男子に比べてはるかに低いものでした。高度成長による好景気と大卒会社員の需要増を迎えても、4年制大学を卒業した女子が社会で活躍できる分野は限られ、女子の就職率はあまり上昇していません。文学部に入学する女子が大多数だったのも、女子が社会科学や理工系の学部に進んでも卒業後の進路が狭く、とくに民間企業では需要が小さかったことが要因と思われます。
この頃週刊誌では「女子学生亡国論」が盛んに取り上げられました。文学部は女子学生で占められ、その多くは卒業して社会に出るわけでも学問を続けるでもなく結婚して家庭に入るのであり、つまり大学で学ぶ目的をもっていない。文学部は花嫁学校化し学問は滅びる、という主張です。早稲田大学の国文学の教授は、「大学は学問の後継者を育て、大学で得たもので社会に役立って行く人物を作ることだ。結婚をひかえた教養のための学問なら、男子を押しのけてまで大学に来なくてもいいと思う」(『朝日新聞』1962年6月4日)と言い切っています。

他方で学習院大学の麻生磯次文学部長は、同じ記事の中で「日本人の半数は女性で、その女性が教養を身につけるため大学教育を受けるのはムダではない。その場合、女性は生来文学に向いているのだから、そのために文学部が女子学部になってもそれで結構だ」と述べています。今見ると「生来文学に向いている」という性差観が気になりますが、「女に学問はいらない」といった古い感覚の持ち主ではなかったことがわかります。そもそも女子学生の増加によって学習院大学の収益が向上していたので、文句は言えなかったでしょう。