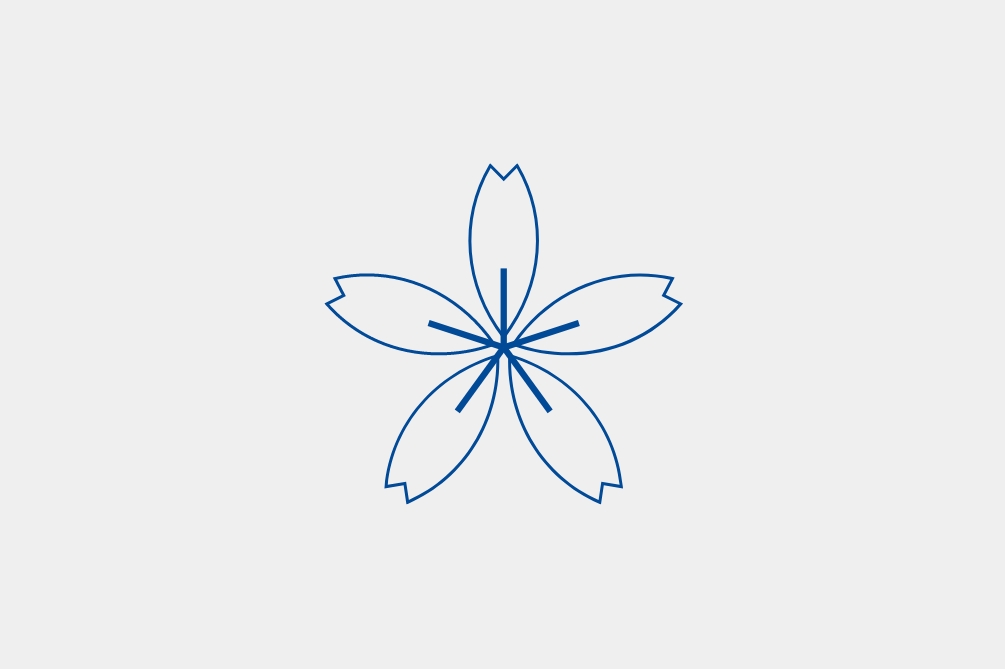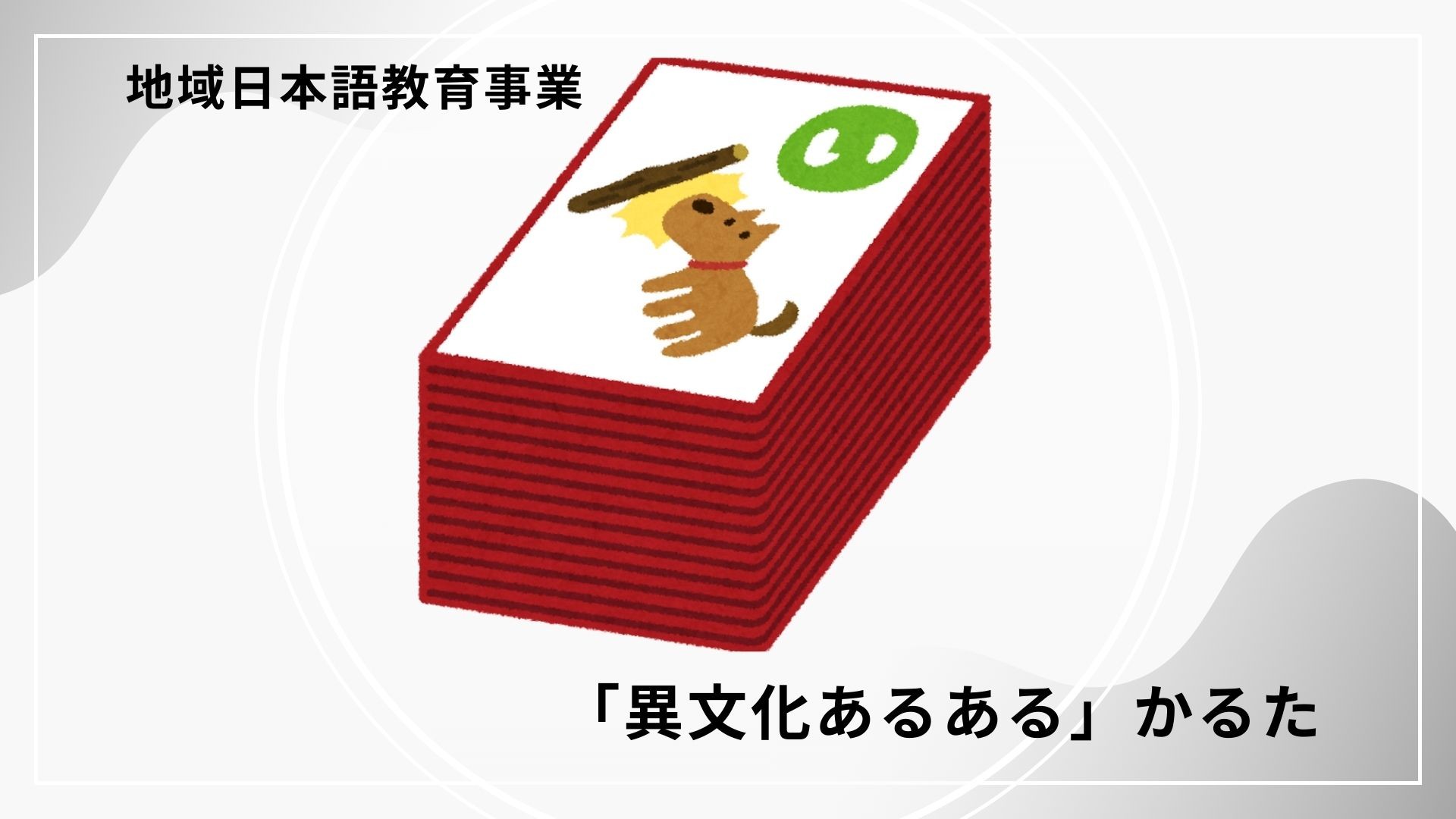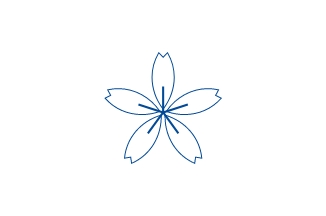規範と逸脱、2つの中心点から日本のポピュラー音楽文化を問い直す
童謡、宝塚、アイドル、さらには「うたのおねえさん」から甲子園の応援演奏まで。近代日本の大衆音楽がいかにメディアと結びつき、社会で育まれたのかを研究する法学部政治学科 周東美材教授。2022年に刊行された『「未熟さ」の系譜 宝塚からジャニーズまで』(新潮選書)では、「未熟さ」というキーワードを軸に日本のポピュラー音楽文化を読み解き、アメリカを"鑑"として独自の進化を遂げた日本の音楽史研究に一石を投じた。「マニアックにはなれない」自身の気質を強みに変え、幅広いフィールドで研究を行う周東教授に話を聞いた。
マニアックに没頭はできないからこそ、
俯瞰の視点からポピュラー音楽を読み解く

― 10代の頃は音楽家を目指されていたそうですが、音楽学と社会学を専攻した後、研究者としてメディア文化史をご専門とされるまでの経緯についてお聞かせください。
もともと音楽や芸術の分野に関心があり、ミュージシャンとして音楽に関わる道を模索していました。ただ、その過程で自身の才能の限界と、練習や音楽活動にのめり込むほどには没頭できない自分の性質に気づきましたので、「それならば音楽の研究者になろう」と思い立ったのがきっかけです。
音楽の研究を通じて最初に興味を抱いたのは「わらべうた」でした。民俗音楽研究者として素晴らしい業績を残されている小泉文夫さんや小島美子さんの研究に興味を惹かれ、学問的に顧みられることのなかった子どもの歌を捉え直す面白さに気付かされました。
もうひとつ、別の理由もあります。私は昔から、特定のジャンルをマニアックに突き詰めるよりも、「誰もが親しんでいるけれども実はあまりわかっていない」分野に興味を惹かれる傾向がありました。
たとえばビートルズのような有名バンドであれば、徹底して深掘りする熱烈なファンや研究者が多数存在します。対して、童謡や幼児向け番組に登場する「うたのおねえさん」などのポピュラー音楽は空気のように当たり前に存在してきたにも関わらず、学問としてはあまり論じられてきませんでした。
没頭は重要なことですが、それゆえに見えなくなる部分もあります。知識量で優劣を競い合う「男性的」な音楽文化ではない、あえて言うならば「女・子ども」向けとして見過ごされてきた音楽文化を俯瞰して捉え直すことで、見えてくるものがあるはずだ。そう確信できたことが現在の研究テーマにつながっています。
― ポピュラー音楽という幅広いフィールドゆえに、研究者としての視点の置き方も難しかったのではないでしょうか。
私は大学を卒業後に大学院浪人を経験しているのですが、その1年間が人生で最もつらい時期でした。ポピュラー音楽というテーマに対する自分の問題意識を、うまく言語化できずにずっと行き詰まっていたんですね。突破口を探してさまざまな本を読む中で出合ったのが、渡辺裕先生のご著書『宝塚歌劇の変容と日本近代』(新書館)でした。
渡辺先生のご専門は音楽美学ですから、私の目指す領域とは必ずしも同じではありませんが、「ああ、こういう風に研究をしていけばいいんだ」といった問いの立て方、問題設定のアプローチがそこでようやく見えてきたんですね。
どれだけ多くレコードを持っているか、どれだけ深掘りして詳しく知っているかといった競争からは降りて、「幼いもの」からの視点で自分は考えていこう。そう思えるようになったことが大きかったですね。
夢と暴力を同時に与えるアメリカを「鑑」として
日本のポピュラー音楽は醸成されてきた
― 近代日本におけるポピュラー音楽は、どのような歴史をたどってきたのでしょうか。
『童謡の近代 メディアの変容と子ども文化』(岩波現代全書)でも論じていますが、子どものための歌として「童謡」が誕生したのは大正時代でした。当時の童謡は都市部で暮らす新中間層の家族のために生み出された、目新しくてモダンで、子どもたちが飛びつくような歌として大流行したのです。
当時の日本は地方から都市部に流れ込んできた人々がサラリーマンとなり、子どもを中心とした家族という新たなライフスタイルを形成していた時期でした。そうした新中間層の中で芽生えた「近代家族」の中心にいた存在が「子ども」です。「子どもを中心とした家庭」が理想の家族像とされ、そこに導入されたのがピアノやバイオリンといった西洋楽器でした。百貨店の休憩室にはピアノが設置され、ミニ・コンサートや家庭向け講演会などが開催されるようになります。

― 女児の習い事として今もピアノが人気であるルーツは、この時期にまで遡るのですね。
そうした近代家族のための音楽という流れで誕生したのが「童謡歌手」でした。1920年代には幼い歌声を持つ歌手たちが、レコードという新しいメディアを続々と出していくこととなりました。意外に思われるかもしれませんが、当時の童謡は最先端の流行でしたので、現代の私たちが抱く「郷愁」のようなイメージが童謡についていくのはずっと後になってからなのです。
女性キャストだけの宝塚歌劇団が誕生したのもほぼ同時期です。当時はそれなりに教育を受けている女の子であっても行動の自由は今より格段に制限されていましたから、「家庭本位」をコンセプトとしていた当時の宝塚は、女子だけでも、家族でも安心して観劇できる貴重な文化の場としての役割を果たしたともいえるでしょう。
ポピュラー音楽を読み解いていくと、家族を中心とするジェンダー規範がどのように形成され、戦後の日本においては「アメリカ」という絶対的な他者とどのように対峙してきたのかが非常によく理解できます。
日本における男性アイドル文化の礎を築いたジャニーズ帝国の崩壊も、その象徴的な例といえるでしょう。ジャニー喜多川氏の存在は、日本のメディアに深く刺さった「アメリカ」という名の棘です。アメリカで生まれ育った彼は、「歌って踊れる男性アイドル」を育成して戦後の日本社会に夢を与えましたが、同時に自身の権力を利用して加害行為を繰り返していました。
これは日本に限らず、アメリカが終戦後、世界中で行ってきたことと同じ構図があり、そこでは「夢」と「暴力」が共存しているのです。ミッキーマウスやハリウッド映画、ジャズやポップミュージック、ハワイのようなビーチリゾートという「夢」を与える一方で、米軍基地という「暴力」を世界中に展開していく。沖縄に今なお米軍基地があり続けることも、すべては根底でつながっています。
この夢と暴力の装置に「占領」されていたのが日本のテレビ業界でした。今はずっと刺さっていた「棘」が抜けかけたものの、それでも元に戻ろうとする強い力が作用している。変化に対する反動や揺り戻しの状態にあるように思えます。
― 2023年は日本の芸能界の闇ともいえる不祥事が噴出した一年でした。メディア文化史の研究者として、日本はここからどのように変化していくと予想されますか。
膿を出し切って大きく変化していくのかと思いきや、実は看板を変えただけで構造的には何も変わっていない。今のメディアをそう見ている人は決して少なくないように思えます。
その背景には日本社会における不均衡なジェンダーバランスが関係している側面もあると考えています。宝塚やジャニーズのファンは女性が圧倒的に多い。熱烈な女性の固定ファンが視聴者となり、買い支えることで成り立ってきた文化です。
「買ってあげる」「支えてあげる」は、どちらも自分より相手が劣位であるからできる行為です。現実が生きづらいからこそ、そうした方法でアイドルに思いを託さざるを得ない女性も少なくはないのではないでしょうか。つまり、この構造は生きづらい女性が多いことの裏返しでもあると私は捉えています。
一方で、アーティスト、創作活動に取り組む人々にとっては、ここからできること、すべきことがたくさんあるはずです。本来、芸術家とは「非常識」なものであり、閉塞した社会に風穴を開け、世界を裏返してみせるポテンシャルを持っている存在です。そういう意味では、この転換点をきっかけにむしろ豊かな文化が生まれていく可能性も大いにあります。

― 構造の変わらなさは課題として残るが、より豊かな文化が生まれる可能性も秘めている。長いスパンで文化を俯瞰し、研究してきた周東先生だからこそ見えてくる視点ですね。
ある時代には「正しい」とされていた価値観が、時代の移り変わりによってそうではないと思われるようになることは多々ありますよね。
これは僕の師匠である吉見俊哉先生がいつも話していることですが、新幹線をどんどんつくっていた時代は「より速い」ことが正解でしたよね。ところが、今は路面電車のように移動の心地よさを感じられる乗り物のほうが生活にフィットしていると感じる人が増えている。社会の価値観は1、2年では変わらなくても、10年、20年、30年と時間が経てばゆっくりと変わっていくものです。
そうした長いスパンでの価値観の変化を捉えられること。社会的な言説がどのように形成されていくのか、その過程と変化を理解すること。それが我々が研究している社会学、そして文系の学問の意義であると私は考えています。20年前にはほとんどの人が興味をもっていなかったLGBTという言葉も、今では広く知られるようになりましたよね。K-POPがここまで日本でムーブメントを起こすことも、誰も想像できなかったでしょう。
― 学生たちと接していて、伝えたいことはありますか。
自分と異なるバックグラウンドを持つ人と多く出会う機会をぜひ見つけてください、とは普段から伝えるようにしています。例えば、未成年にはあまり推奨できないかもしれませんが、新宿なり渋谷なりで終電を逃して朝まで時間を潰さないといけない状況になったとします。そうしたら、どこかのお店に入ってみて、隣に座ったおじさんやおばさんと会話をして、できれば友達になってみる。イメージとしてはそんなところですが、別にボランティア活動でも遊びや趣味の世界でもかまいません。大切なのはバックグラウンドがまったく違う人と出会うことです。
教室の中で人気者かどうか、陰キャか陽キャか、そうした似た者同士だけの世界でずっと生きていても、本当のコミュニケーション能力は身につきません。年齢も、性別も、学歴も、社会的背景も、価値観もまったく異なる相手との対話によってしか、根本的な自己変容は起きないからです。
「それならば海外留学をしよう」と考えるかもしれませんが、国籍が違うだけで実は自分と近い属性の人としか出会えない可能性もありますね。語学学校や滞在先で、日本人の友だちとばかり親しくなってしまうかもしれません。留学はもちろんとても貴重な経験ですからどんどん行っていただきたいのですが、そうした側面もある事実は知っておいていいでしょう。
SNSや狭い世界で自分の「正しさ」だけに固執してしまうと、いつまでもその正しさの檻から出られなくなります。例えば、学校という世界の中では、「子どものいない夫婦」に出会う機会はほとんどありませんが、学校の外にはそういう生き方を選んでいる大人たちもいます。だからこそ、異質な他者と出会い、自分の思い込みや価値観をリセットする。自分の殻を脱いでいく経験を若いうちからぜひ積み重ねてもらえたらと思います。
クィア文化アーカイブ化によって
「逸脱者」の歴史を浮かび上がらせたい

― 研究者としての周東先生の今後の展望を教えてください。
一見すると相対的な位置にある、2つの中心点を持つ楕円のような研究テーマを並行して進めていくつもりです。
『「未熟さ」の系譜』では家族制度やジェンダー規範などの価値観に依拠して、童謡や宝塚、アイドル文化の形成を考えてきましたが、そもそもの制度や規範があまりに硬直しているとも感じました。
「家族は素晴らしいものだ」「子どもを産まないと幸せになれない」「なぜ結婚しないのか」
こうした価値観が長らく呪縛のように機能してきたのが日本社会です。けれども家族を支えているのは経済ですから、それが立ち行かなくなったことで新中間層が没落し、若い世代を中心に「家族」が形成できない時代へと変化していきました。性別役割分業や異性愛主義に支えられた家庭イデオロギーが、ジェンダーをめぐる問題によって、根本から問い直されているのです。
すでに強固に形作られ、制度化されてきた規範を歴史的に検証していきたい。これが今までの私の研究におけるひとつの中心点です。
他方で、私の中には「これらの硬直化した規範に揺さぶりをかけたい」という思いも研究者となった当初からずっと存在しています。家族や制度を支えてきたジェンダー規範を問い直す。そのための研究のひとつとして取り組んでいるのがクィア文化のアーカイブ化です。
日本のドラァグクィーンの草分け的存在であり、ゲイ雑誌『バディ』の編集長代行を務めたマーガレット(本名:小倉東)さんが個人的に集めてきたLGBT関連の蔵書が約1万8000点あるのですが、それらすべての目録を作成し、デジタルアーカイブ化することを目指しています。
差別的なもの、ゴシップ的なもの、書店に流通しないものは入れないといった価値判断はあえて行わず、過去を忘れないためにすべてを残していく方針です。
― 規範と逸脱、対極にある2つの視点を行き来することによって、社会を見る新たな視点が獲得できるように思えます。アーカイブ作業はいつ頃から着手されていたのでしょう
作業を始めたのは2022年5月26日です。作業日誌を振り返って気づいたのですが、『「未熟さ」の系譜』が刊行されたちょうど翌日でした。
制度化され、構造的なものと結びついてきた文化について論じた本が出た翌日から、それらに楔を入れるような研究を始めているのが我ながら面白いなと感じていますね。手弁当の少人数で行っている作業ですから、ここから何十年もかかるだろうと覚悟しています。
― 身近なポピュラー音楽や芸能の世界の見え方が変わったのはもちろん、長い時間をかけて価値を発揮していく文系学問の在り方もあらためて教えられた気がします。本日はありがとうございました。


Profile
周東 美材
YOSHIKI SHUTO
1980年生まれ。早稲田大学第一文学部卒業、東京大学大学院学際情報学府修了、博士(社会情報学)。専攻は社会学、音楽学。東京大学大学院特任助教、日本体育大学准教授、大東文化大学准教授を経て、2023年4月より学習院大学法学部教授。著書に『童謡の近代』(岩波現代全書、第46回日本童謡賞・特別賞、第40回日本児童文学学会奨励賞)、『カワイイ文化とテクノロジーの隠れた関係』(共著、東京電機大学出版局、2016年日本感性工学会出版賞)、『「未熟さ」の系譜』(新潮選書)など。